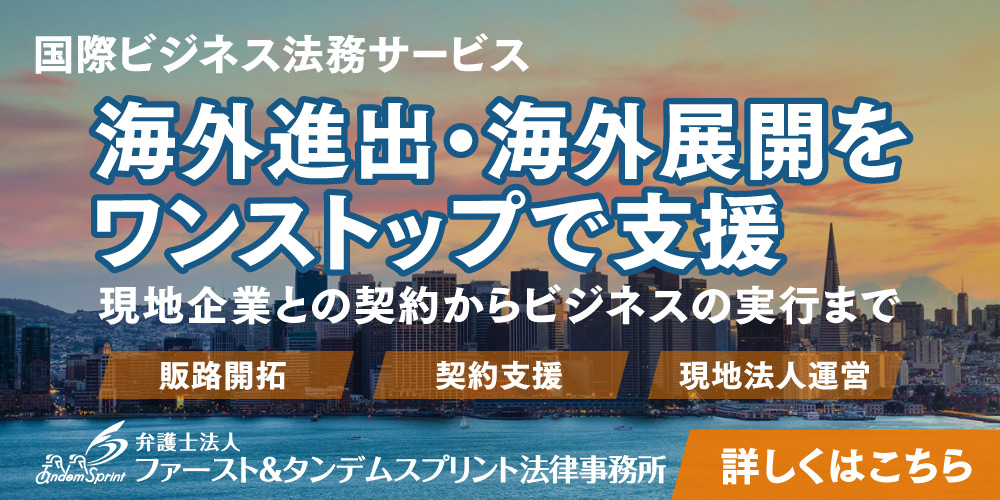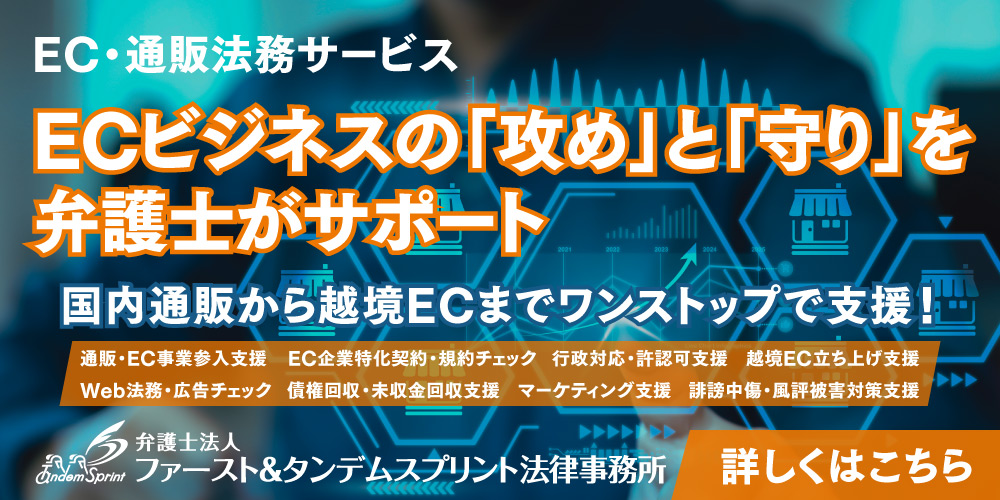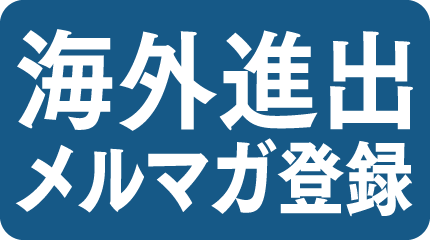目次
海外におけるライブコマースの現状と市場動向

ライブコマースとは、ライブ配信を通じて商品やブランドを紹介し、リアルタイムで視聴者が購入できる仕組みです。従来のECサイトに比べて「視覚的な情報量の多さ」や「双方向のやり取り」が可能な点が特徴で、海外ではすでにサービスの一環として大きな市場を形成しています。
特に中国をはじめとするアジアでは、ライブコマースがECの売上を押し上げる重要なマーケティング手段となっており、アメリカやヨーロッパでも2023年以降、注目度が急速に高まっています。企業やサービス提供者にとって、海外市場へのアプローチにおいて新たな販売チャネルとして欠かせない方法のひとつになりつつあるのです。
国別のライブコマース市場分析

中国のライブコマース市場
中国は名実ともに世界最大級のライブコマース市場であり、その成長スピードも群を抜いています。中国商務部や各種調査会社のデータによると、中国のライブコマース市場規模は年々拡大を続けており、ここ数年は年平均成長率(CAGR)20〜30%前後で推移しています。2025年には数十兆円規模に達すると予測されており、EC市場全体の売上の2割以上をライブコマースが占めるという試算も出ています。
主要プラットフォームの特徴
- アリババ(タオバオライブ):ライブコマースの先駆者的存在。膨大な商品ラインナップと安定した物流網を背景に、日用品から高級品まで幅広い販売を展開。インフルエンサーや「トップKOL」の登用により、短時間で巨額の売上を生み出す事例が多数あります。
- JD.com(京東):信頼性の高い商品と配送スピードが強み。テクノロジー活用によるデータドリブンな配信で、消費者の購買行動を分析・最適化する仕組みを整えています。
- Douyin(中国版TikTok):エンタメ性と拡散力に優れ、若年層を中心に人気。短尺動画からライブ配信への誘導がスムーズで、衝動買いを促しやすいのが特徴です。
- Kuaishou(快手):地方都市や農村部のユーザーに強い基盤を持ち、アリババやJDが届きにくい市場をカバー。より「生活密着型」の商材が売れやすい環境を形成しています。
消費者動向の分析
中国の消費者、とくにZ世代やミレニアル世代は、単に商品を購入するだけでなく「エンターテインメントとしての購買体験」を重視しています。ライブコマースでは以下のような行動が見られます。
- リアルタイムの信頼性確認:配信中の質問やレビューを通じ、購入前に疑問を解消する傾向が強い。
- ブランドよりもインフルエンサー重視:消費者はブランド名よりも「誰が紹介しているか」を重視する傾向があり、人気KOLの発言が購買行動を左右します。
- 高い購買力:都市部の若年層は、ファッション、コスメ、デジタル製品など「高い単価の商品」でも即決購入することが多い。
- 地域ごとの違い:一線都市ではブランド志向が強いのに対し、二線・三線都市では「お得感」や「限定感」が購買の動機になりやすい。
アメリカのライブコマース市場
アメリカは中国に比べるとまだ市場規模は小さいものの、急速に拡大中です。調査会社によれば、アメリカのライブコマース市場は2022年に約200億ドル規模に達し、今後も年平均成長率20%以上で拡大し、2026年には700億ドルを超えると予測されています。特にファッション、ビューティー、家電カテゴリーでの伸びが顕著です。
主要プラットフォームの特徴
- AmazonLive:アメリカ市場で最も代表的なプラットフォーム。既存のEC基盤を活かし、ブランド公式チャンネルやインフルエンサーを起用した配信を展開。信頼感のある商品紹介が強みです。
- InstagramLiveShopping:SNSとの連動性が高く、ファッションやコスメ系ブランドが積極的に活用。ユーザーはそのままアプリ内で購入できる利便性が魅力です。
- TikTokLiveShopping:若年層を中心に利用が拡大。短尺動画からライブへのシームレスな導線により、エンタメ感覚で購買体験を提供。
- YouTubeLiveShopping:動画プラットフォームとしての信頼性が高く、長尺のレビューや比較紹介に強み。家電やガジェットといった高価格帯商品の販売に適しています。
消費者動向の分析
アメリカの消費者は「情報の透明性」を重視する傾向が強く、以下のような特徴が見られます。
- レビュー文化の影響:商品の使用感をリアルタイムで確認し、レビューや他者のコメントを参考に購入を決断。
- ブランド信頼重視:中国のようにインフルエンサー頼みではなく、ブランド自体の信頼性や企業姿勢が購買に影響。
- 若年層の急速な取り込み:Z世代はSNSを通じたライブショッピングをエンタメの一環として楽しむ傾向が強く、将来的な市場成長を牽引。
- 高価格帯への抵抗感:中国に比べて衝動買いは少なく、「中価格帯商品」や実用的アイテムの購入が中心。
東南アジアのライブコマース市場
東南アジアは、スマートフォン普及とEC成長が重なり、世界でもっとも急成長している市場のひとつです。GoogleやTemasekの調査によると、東南アジアのデジタルコマース市場は2025年までに3000億ドル規模に達すると予想され、その中でもライブコマースが大きな割合を占める見込みです。国によって差はありますが、成長率は年30%以上と非常に高水準です。
主要プラットフォームの特徴
- ShopeeLive:シンガポール発のShopeeが展開するライブ配信機能。割引やバウチャー配布を組み合わせ、エンタメ性の高い配信が人気。
- LazadaLive:アリババ傘下のLazadaが提供。中国のノウハウを活かし、インフルエンサー活用やゲーム感覚の配信で購買意欲を刺激。
- TikTokLiveShopping:ベトナムやインドネシアなどで急拡大。特にZ世代ユーザーが日常的に利用し、ファッションやコスメの売上を伸ばしています。
- FacebookLiveCommerce:依然として東南アジアで根強い人気。個人事業主や中小企業が手軽にライブ販売を始められる点が強み。
消費者動向の分析
東南アジアの消費者は、購買行動において「価格」「エンタメ性」「信頼性」の3要素を重視しています。
- 価格志向の強さ:経済発展途上の国も多く、中価格帯や低価格帯商品の需要が大きい。割引キャンペーンやフラッシュセールに強く反応。
- エンターテインメント型購買:買い物そのものを楽しむ傾向があり、ライブ中のゲームやプレゼント企画が効果的。
- モバイルファースト:スマホ経由での利用率が圧倒的に高く、配信は短時間でテンポ良いものが好まれる。
- ブランドより人ベース:ローカルのインフルエンサーや販売者への信頼感が購買を左右。身近さや親近感が決め手になることが多い。
海外の成功事例とその特徴

中国の成功事例:アリババのライブ配信
アリババは「タオバオライブ」を軸に、世界最大規模のライブコマース市場をけん引しています。その特徴は以下の通りです。
・アリババのプラットフォーム活用
タオバオやTmallなど既存の巨大ECプラットフォームとシームレスに連携。配信から購入まで一貫して完了できるユーザーフローを構築し、消費者の離脱を防いでいます。
・インフルエンサーとの連携
トップKOL(キーオピニオンリーダー)や人気インフルエンサーを活用し、膨大な視聴者を集客。消費者は「誰が紹介するか」に強い関心を持ち、商品の魅力をより信頼性のある形で受け取ります。
・リアルタイムのインタラクション
配信中にコメントや質問を受け付け、販売者やインフルエンサーが即座に回答。疑問が解消されることで購入率が高まり、「参加型購買体験」が強力な差別化要素となっています。
アメリカの成功事例:AmazonLive
アメリカではAmazonLiveが代表的事例として注目されています。既存のEC基盤を活かしながら、ライブ配信の可能性を広げています。
・商品の魅力を引き出すプレゼンテーション
AmazonLiveでは、商品レビューやデモンストレーションに重点を置き、特徴や使用感をわかりやすく解説。特に家電や美容アイテムでは「実際の使用シーン」を見せることで、購買意欲を高めています。
・視聴者参加型の企画
クーポン配布や限定セール、チャット機能を通じた質問コーナーなどを実施。消費者は「ただ見るだけ」ではなく、ライブに参加する楽しみを感じられるため、ブランドとのつながりが強化されます。
・データ分析による最適化
Amazonは視聴時間、クリック率、購入率などのデータ分析を徹底的に行い、次回配信に反映。最適な配信時間帯や商品カテゴリを導き出し、効率的な販売を実現しています。
ヨーロッパの成功事例:Zalando
ドイツ発のファッションEC大手Zalandoは、ヨーロッパ市場でライブコマースの新しい形を確立しています。
・ファッションに特化したコンテンツ
モデルによるコーディネート提案やライブ試着イベントを展開。消費者が「実際に着たときのイメージ」を持ちやすく、ファッション特有の購買不安を払拭しています。
・ユーザー生成コンテンツの活用
一般ユーザーのレビュー動画やSNS投稿を配信内で紹介することで、リアルな消費者の声を活かしています。これによりブランドの信頼性が増し、購買意欲を後押しします。
・ブランドとのコラボレーション
有名ブランドや新進気鋭のデザイナーとコラボし、ライブ限定コレクションや特別アイテムを販売。希少性と話題性を掛け合わせ、短時間で大きな売上を記録する成功事例が生まれています。
アリババ、Amazon、Zalandoに共通しているのは、単に「ライブで商品を売る」だけではなく、
- プラットフォームの強みを最大化
- 消費者を巻き込む参加型体験
- データやユーザーの声を活用
といった多角的な戦略を組み合わせている点です。越境ECを狙う企業にとっても、これらの事例は「市場や文化に合わせて何を強調するべきか」を学ぶ上で大きな参考になります。
ライブコマースのメリットとデメリット

メリット
ライブコマースの最大の強みは、視聴者とのインタラクションにあります。消費者は配信中に質問を投げかけたり、コメントを通じて意見を共有したりすることで、単なる「視聴者」から「参加者」へと変わります。この双方向性は心理的な距離を縮め、購買意欲を高める重要な要因となります。
さらに、リアルタイムでのデモンストレーションは大きな説得力を持ちます。たとえば、コスメ商品であればインフルエンサーが実際に使用して発色や質感を見せる、家電であれば操作方法を実演する、といった形です。消費者は「写真やテキストでは分からない情報」をその場で確認できるため、購入決定のハードルが下がります。
また、ライブ中に質問を投げれば即座に回答が得られるため、不安や疑問が解消され、衝動買いを後押しする効果があります。ここに、実際の使用例や既存顧客の体験談を取り入れることで、ブランドの信頼性はさらに高まります。視聴者は「リアルな声」を聞くことで、商品やブランドへの安心感を得やすくなるのです。
デメリット
一方で、ライブコマースには課題も存在します。
まず、技術的なトラブルです。配信の途中で映像や音声が乱れる、システム障害が発生する、といった問題が起きると、視聴者の満足度は大きく下がり、購買機会の損失につながります。特に販売ピーク時のトラブルは、ブランドイメージの低下にも直結しかねません。
次に、視聴者の参加意欲の差による不安定さです。ある配信では多くの参加者が集まり高い売上を記録しても、別の配信では参加者が少なく思うように成果が出ないこともあります。この不安定さは、ブランドや企業がライブコマースにリソースを投資する際のリスク要因となります。
さらに、競争の激化も見逃せません。多くの企業やブランドがライブコマースに参入するなかで、単に商品を紹介するだけでは差別化が難しくなっています。結果として「どのブランドも同じように見えてしまう」状況が生まれ、消費者の注目を引くのが難しくなるのです。
そのため、成功のためにはユニークな企画や独自のストーリーテリングを取り入れるなど、他ブランドとの差別化戦略が不可欠です。単なる販売促進ではなく、「視聴者が参加したくなる体験」を設計することこそが、ライブコマースにおける長期的な競争優位につながります。
成功するライブコマースの戦略

インフルエンサーの活用
越境ECにおいては、現地の文化や購買習慣に精通したインフルエンサーを起用することが欠かせません。消費者は、見知らぬブランドよりも「信頼する人物の推薦」に強く反応します。たとえば、中国ではKOL(キーオピニオンリーダー)、東南アジアではローカルのマイクロインフルエンサーが購買行動を左右する大きな存在です。
文化適応の重要性:国によって好まれる配信スタイルや表現は異なります。アメリカの視聴者にはフランクで情報性の高いレビューが響き、中国の視聴者にはカリスマ的なインフルエンサーの影響力が強く作用する傾向があります。
インフルエンサーのタイプ:フォロワー数が数百万人規模の「トップインフルエンサー」だけでなく、数万人規模でも特定の分野で信頼を築いている「マイクロインフルエンサー」の活用も効果的です。ニッチな市場や特定カテゴリーの商品では後者の方が購買意欲を高めやすいケースも多く見られます。
ブランドとの協働:一方的な紹介ではなく、ブランドと共同で企画を立て、商品のストーリーを語らせることが、越境ECにおける認知拡大と信頼性強化につながります。
双方向コミュニケーションの重要性
ライブコマースは、単なる「映像広告」ではなく、視聴者と販売者が会話する場です。視聴者はコメントを通じて商品に関する疑問を投げかけ、配信者が即座に回答することで「自分専用の接客を受けている」という感覚を持ちます。
リアルタイム対応の効果:質問や懸念がその場で解消されるため、購入決定までの心理的ハードルが大幅に下がります。
特別感の演出:名前を呼んでコメントに答える、質問者限定の割引コードを配布するといった工夫は、参加者に「自分が特別扱いされている」と感じさせ、購買行動を後押しします。
コミュニティ化:リピーター視聴者が集まると、配信は単なる販売の場から「コミュニティ」へと発展。結果としてブランドロイヤルティの強化にもつながります。
ターゲット層の明確化
成功するためには、「誰に向けて配信するか」を明確にすることが最重要です。漠然と「すべての消費者」に向けた配信は効果が薄く、むしろ視聴者が離れてしまいます。
価格帯ごとのアプローチ:
中価格帯の商品:日常使いのアパレルや生活雑貨では、実用性やコストパフォーマンスを前面に出すと効果的。
高価格帯・ブランド商品:高級コスメやデザイナーズブランドでは、限定感やブランドストーリーを強調し、aspirational(憧れを喚起する)要素を打ち出す必要があります。
ターゲット層の行動特性:Z世代はエンタメ性やインタラクションを重視し、ミレニアル世代はレビューや信頼性を重視する傾向があります。配信スタイルを層ごとに変えることで、より高い効果が期待できます。
パーソナライゼーション:データ分析を用いて、どの層がどの商品に反応しているかを把握し、次回以降の配信内容を最適化していくことが長期的な成果につながります。
ライブコマースの未来展望

技術革新とライブコマース
今後のライブコマースは、AIやAR/VR技術の導入によって、従来以上にインタラクティブでパーソナライズされた購買体験を提供できるようになります。
AIの活用
AIは視聴者の行動データや購買履歴を分析し、配信中に最適な商品をレコメンドしたり、個別にクーポンやキャンペーン情報を表示したりできます。たとえば、AmazonLiveではAIを用いて、視聴者の過去の購入傾向や閲覧履歴に基づきリアルタイムで商品を提示する仕組みが開発されています。これにより、購買確率の向上や離脱率の低減が期待できます。
AR/VR技術の導入
AR(拡張現実)を活用することで、消費者はスマートフォンやタブレットを通じて、商品を自宅で試着・配置できるようになります。ファッションでは試着シミュレーション、家具や家電では部屋への設置イメージが可能です。VR(仮想現実)を活用すれば、バーチャル空間での展示会やショッピングモール体験をライブ配信と組み合わせ、まるで現地で買い物をしているかのような没入型体験が提供できます。
プラットフォームの進化
主要プラットフォームも技術革新に対応しています。TikTokやInstagramは、ARフィルターや3D表示を取り入れたライブ配信機能を強化。ZalandoやAmazonではAI分析を用いたおすすめ商品の表示や、インタラクティブ投票機能など、新しい機能が次々と導入されています。これにより、ライブコマースは単なる販売チャネルから、エンターテインメント型購買体験へ進化しています。
消費者行動の変化
オンラインショッピングは世界的に普及しており、日本でも総務省の統計によると、2024年時点で全消費者の約70%がオンラインで商品を購入しています。特に若年層はスマートフォンを通じたショッピングが日常化しており、ライブ配信を通じた購入も増加しています。
ライブ配信人気の背景
①リアルタイムで商品情報を得られること
②視聴者が配信に参加できる双方向性
③エンターテインメント要素と購買行動が融合していること
これらの要素が、従来のECサイトでの静的な購入体験に比べて消費者に「楽しく、納得感のある購買」を提供しています。
購買決定プロセスの変化
従来は「商品を比較してレビューを確認→購入」でしたが、ライブコマースでは「配信中にデモンストレーションを確認→コメントや質問で不安を解消→即購入」が可能になっています。このプロセス変化により、購買までの意思決定時間が短縮され、即時購入率が高まる傾向があります。
具体例
- 中国のタオバオライブでは、ライブ中のコメント応答やデモンストレーションにより、商品の売上が数分で数百万円規模に達することもあります。
- AmazonLiveでは、AIによるおすすめ商品提示と配信者のデモンストレーションを組み合わせることで、従来よりも購入単価が20%以上上昇した事例があります。
日本市場におけるライブコマースの可能性

日本のライブコマース市場の現状
日本のライブコマース市場は、ここ数年で急速に成長しています。矢野経済研究所の調査によると、2024年の日本のライブコマース市場規模は約500億円と推定され、2026年には年平均成長率20%以上で拡大すると予測されています。特に20〜30代の若年層の消費者に支持されており、スマートフォンで手軽に視聴・購入できる点が受け入れられています。
・消費者の購買意欲と参加意識
日本の視聴者は、単なる視聴だけでなく「コメントや質問を通じて参加したい」という意識が強く、配信中に双方向のやり取りがある場合、購入率が高まる傾向があります。特に美容・ファッション・食品などの分野で、リアルタイムで使用感やコーディネートを確認できる商品が人気です。
・人気商品カテゴリー
- コスメ・スキンケア商品:実際の使用感や仕上がりを確認できるため人気
- ファッション・アクセサリー:着用イメージの確認やコーディネート提案が効果的
- 家電・ガジェット:操作性や使用感のデモンストレーションが購買意欲を刺激
競合他社の動向と成功戦略
日本国内では楽天やYahoo!ショッピング、AmazonJapanなどがライブコマースを導入し、独自の企画やキャンペーンを展開しています。成功している企業は次のような戦略を採用しています。
- インフルエンサーや専門家を活用して信頼性を高める
- 視聴者参加型企画(クーポン配布・抽選・コメント対応)でエンゲージメントを高める
- 限定商品やタイムセールを組み合わせ、購買意欲を喚起する
海外の成功事例から学ぶ
海外の成功事例は、日本市場に応用できる多くのヒントを提供します。
- アリババ(中国):インフルエンサーとの連携とリアルタイムインタラクションにより、参加型の購買体験を提供
- AmazonLive(アメリカ):商品の魅力を引き出すプレゼンテーションとデータ分析による最適化で効率的な販売
- Zalando(ヨーロッパ):ファッションに特化したコンテンツやユーザー生成コンテンツの活用でブランド信頼を強化
これらの成功要因を日本市場に応用する場合、例えば以下のような戦略が考えられます。
- 若年層向けに特化した配信時間やコンテンツ設計
- 日本独自の文化やトレンドを取り入れたインフルエンサー活用
- リアルタイムでの質問対応や使用感デモを重視した参加型配信
- 限定商品やコラボ企画による話題性の創出
ライブコマースを活用した越境ECの可能性

越境ECとライブコマースの相乗効果
ライブコマースは、越境ECにおける商品の魅力を最大限に伝えるツールとして非常に有効です。
視覚的魅力の訴求
商品をリアルタイムで見せながら説明できるため、テキストや写真だけでは伝わりにくい質感や使用感、サイズ感を視聴者に体験させることができます。ファッションでは着用イメージ、化粧品では色味や仕上がり、家電では操作方法をライブで示すことで、購買への不安を大幅に軽減できます。
リアルタイムでの双方向コミュニケーション
視聴者からの質問に即座に回答したり、コメントに反応したりすることで、ブランドや販売者への信頼感が醸成されます。特に越境ECでは、商品の品質や配送への不安を解消することが購入決定に直結します。
このように、ライブコマースは「視覚的体験×双方向コミュニケーション」という特徴を活かして、越境ECの成功率を高める強力な手段となります。
海外市場へのアプローチ方法
越境ECでライブコマースを活用するには、以下のステップが重要です。
1.ターゲット市場のリサーチ
どの国や地域にどのようなニーズがあるのか、競合状況や消費者の購買行動を分析します。たとえば、中国市場では若年層向けのファッションや美容商品が人気であり、米国では家電や日用品がライブコマースで売れやすいといった傾向があります。
2.現地文化や消費者行動の理解
単に商品を海外に送るだけでは成功しません。現地の嗜好、配信スタイルの好み、決済方法、物流環境などを考慮した商品・サービス設計が求められます。たとえば、東南アジアではエンタメ性の高い配信が好まれるため、ゲーム感覚のキャンペーンやインタラクティブな企画が効果的です。
3.ライブコマースを活用したプロモーション戦略の策定
- 商品デモンストレーション:商品の使用方法や特性をライブで紹介
- インフルエンサー活用:現地で信頼性の高い人物を起用して購買意欲を喚起
- 参加型企画:リアルタイム質問、クーポン、抽選などで視聴者を巻き込み、購入体験を楽しませる
- 限定商品・コラボ企画:希少性や話題性を作ることで、短期的な売上向上につなげる
このような施策を組み合わせることで、単なる商品販売にとどまらず、ブランド認知向上×購買体験の向上を同時に実現できます。
まとめ・専門家に相談

ライブコマースは、単なる「一時的な流行」ではなく、今後のEC戦略における必要不可欠な販売方法として位置づけられます。特に越境ECにおいては、海外市場での販売成功がブランド成長や売上拡大に直結するため、戦略的なアプローチが欠かせません。
本記事で紹介したように、成功事例から学べるポイントは多岐にわたります。
- プラットフォーム活用:アリババやAmazon、Zalandoのように、自社ECやSNSと連動した購買体験の設計
- インフルエンサー連携:現地文化に合った信頼性の高い人物を活用し、購買意欲を高める戦略
- リアルタイムコミュニケーション:視聴者参加型の双方向体験で信頼性を醸成
- データ分析と最適化:視聴者行動や購入データを分析し、配信内容やプロモーションを改善
- 商品体験の可視化:AR/VRやライブデモによる体験価値の提供で購買ハードルを低減
これらを踏まえて戦略を立てることが、国内外問わずライブコマースで成果を上げるための基本です。
しかし、越境ECでは単に配信を行うだけでは成果につながらず、言語・文化・法律・物流・決済など、多くのハードルがあります。
- 配信内容やプロモーションの現地適応
- 税関や輸出入規制への対応
- 安全かつ迅速な物流の確保
- 現地決済手段の整備
これらを個人や小規模企業が独力でカバーするのは容易ではありません。したがって、ライブコマースを活用して越境ECを成功させたい場合は、専門家や経験豊富な会社に相談することが最も確実な第一歩です。
専門家は、以下のような支援を提供できます。
- 現地市場や消費者動向のリサーチ
- 配信企画・インフルエンサーキャスティング
- 法律・税務・物流面でのアドバイス
- 効果測定や次回配信への改善提案
最初から完璧な戦略を作ろうとせず、専門家のサポートを受けながら小規模テスト配信→データ分析→スケールアップのプロセスを踏むことが、成功への近道となります。