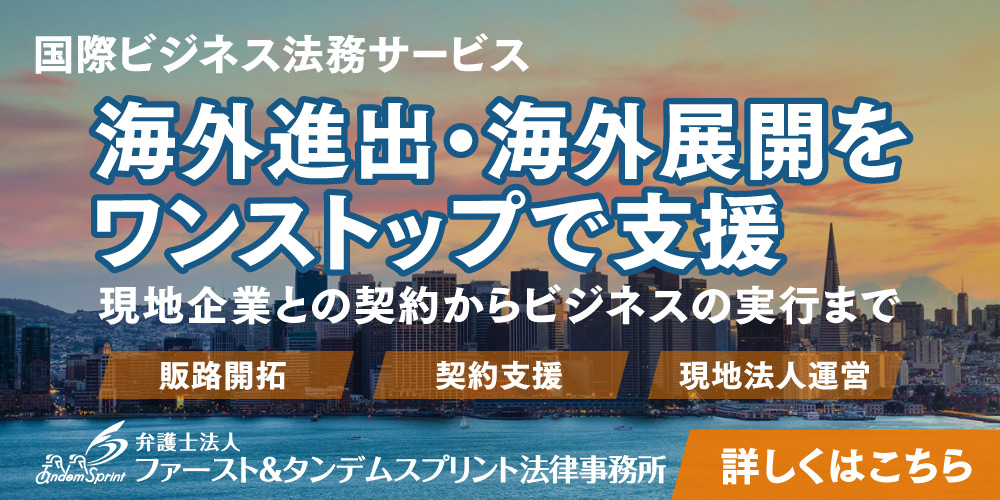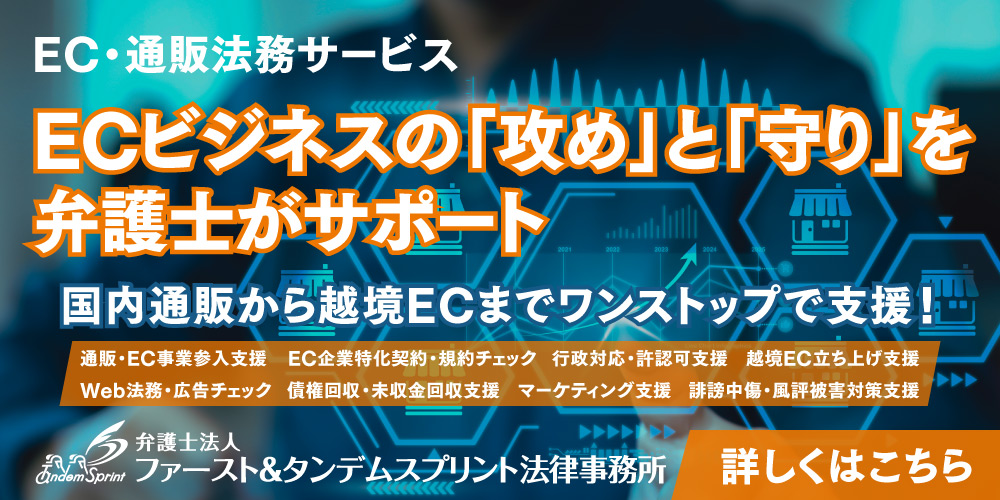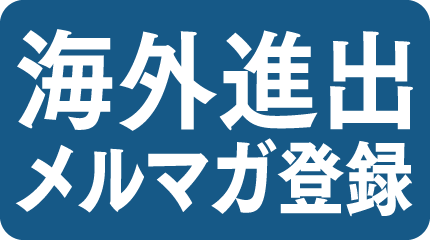目次
1. はじめに

現代のグローバル市場では、海外展開のハードルが年々低くなっており、特に越境ECの利用がその動向を加速させています。化粧品業界では、国内市場の成長が頭打ちになりつつある中で、越境ECを活用することにより、新たなビジネスの拡大が期待されています。日本製化粧品は、その高品質と独特の魅力で国際市場でも高い競争力を持ち、世界中で着実にシェアを拡大しています。さらに、消費者の購買行動が多様化し、国境を越えた商品流通が一般化することで、これらの製品への需要がますます高まっています。
このような市場環境の中で、自社サイトを通じて海外にリーチする手法もありますが、ゼロからのウェブサイト構築やマーケティング導入には膨大な時間と労力が必要です。また、知識や経験が不足していると、期待した結果が得られないおそれもありますより効率的なアプローチとして、化粧品販売に特化した既存の越境ECプラットフォームの活用も検討できるでしょう。これらのプラットフォームは国際的な顧客基盤を既に持っており、多言語対応や現地法規に適応しているため、新規市場への進出がスムーズに行えます。
ただし、モール型ECを活用する場合には、手数料や独自ブランディングの制限といったデメリットも存在します。自社の戦略や製品特性に応じて、どの販売チャネルが最適かを見極めることが重要です。消費者の需要を深く理解し、適切なECプラットフォームを選定することで、グローバル市場での販売機会を最大限に捉え、企業成長を加速させることが可能になります。越境ECは、国内市場だけでなく、世界中の市場へと事業を広げるための強力なツールとなり得ます。この記事では、越境ECを活用した化粧品ビジネスを介して新たな顧客層を獲得するための戦略を探ります。
2. 越境ECにおける化粧品販売の全体像
2-1. 市場規模

越境ECにおける化粧品販売の市場規模は、日本企業にとって大きなビジネスチャンスを示しています。全国調査によると、日本が中国に輸出した越境ECの総額は約1兆5,345億円に達し、これは対米輸出総額の8238億円のほぼ2倍に相当します。このデータは、中国市場のポテンシャルの高さを示しており、特に化粧品カテゴリーでは顕著です。日本製品の品質への信頼感から、中国人の消費者の間で高い人気を誇っています。
一方、米国市場も巨大であり、日本からの化粧品含む製品の対中輸出総額は1兆7278億円にのぼります。これらの数字から、北米とアジアの性質はそれぞれ異なりますが、これらの世界的主要二市場がいかに重要であるかが伺えます。両市場では消費者の購買傾向や規制も異なるため、それぞれに最適化した戦略や施策が求められます。
さらに、Shopee(東南アジア・台湾で最大規模の越境ECプラットフォーム)の消費者トレンド分析によると、2023年第一四半期における日本越境商品の人気カテゴリー1位が「美容品・化粧品」となりました。これは、アジア全域における日本製化粧品の高い評価と需要を示しています。
こうした状況を踏まえると、越境ECで化粧品販売を始めることは、低リスクかつ高成長が期待できる戦略として非常におすすめです。特に海外への実店舗展開や卸売と比較して、輸入にかかるコストや在庫管理の負担が軽減され、効率的な国際展開が可能です。
ただし、越境ECには国ごとの法規制や税制への対応、輸出および輸入の手続きなど、多くの実務対応が伴います。正確な情報収集と現地ニーズの理解を踏まえた対応が不可欠であり、法務や物流に精通したパートナーとの連携が成功の鍵を握ります。
これらのデータを基に考えると、越境ECを通じた化粧品販売は、日本企業がグローバル市場でのプレゼンスを高め、経済的利益を拡大するための有力な手段です。国際的なブランド認知度の向上にも寄与し、長期的なビジネス拡張に繋がる可能性が高いことが期待できます。
2-2. 実施事例
越境ECを活用した化粧品販売の成功例として、「SK-II」と「ライスフォース」が挙げられます。これらのブランドは異なる戦略を採用し、国際市場での地位を確立しています。
「SK-II」は1980年に創立された日本のプレミアムスキンケアブランドで、中国市場での存在感が特に目立っています。中国で高級化粧品のカテゴリーに位置づけられ、多数の実店舗とオンラインショップで製品・サービスを展開しています。SK-IIは個別製品の販売に加え、バリューセットを提供することで平均販売価格を引き上げ、利益を増大させています。資生堂と肩を並べるブランド認知と顧客のリピート購入率は、洗練された製品戦略の成果です。
一方で、「ライスフォース」は、株式会社アイムによって運営される薬用化粧品ブランドです。このブランドは、30代から50代の女性を主なターゲットとしており、日々の生活や旅行の光景、食事の情報を提供することで顧客との繋がりを深め、共感を生み出しています。無名の状態からスタートしたライスフォースは、その後、売上を飛躍的に伸ばし、国際的な評価を獲得しています。特に海外では、リゾートホテルやスパでのアメニティ提供を展開し、越境ECを通じて製品を積極的に販売しています。また、Instagramでの魅力的な商品画像の共有や、それをECサイトのレビューコンテンツとして再活用する戦略が、さらなる売上増加を促しています。
3. 越境ECが注目される理由
近年、化粧品業界において越境ECが注目を集めている背景には、いくつかの要因があります。特に日本のコスメ製品は、世界的に高く評価されており、その品質やブランド力が越境ECにおける大きな強みとなっています。さらに、国内市場の縮小に伴い、多くの企業が成長機会を海外に求める傾向が強まっており、越境ECはその手段として魅力的です。加えて、従来よりも低コストで海外販売に参入できる仕組みが整ってきたことで、参入障壁が下がり、多くの企業にとって現実的な選択肢となりつつあります。以下では、こうした注目の背景について詳しく解説していきます。
3-1. 日本の化粧品の評価が世界的に高い

日本製の化粧品は、世界中の消費者から「信頼できる品質」として高く評価されており、越境ECにおける有力な商材の一つです。その背景には、製造・品質管理に対する厳格な基準と、日本独自の研究・開発技術があります。肌へのやさしさや安全性が徹底されており、敏感肌をもつユーザーからも支持されやすいことが、海外市場での大きなアドバンテージとなっています。
また、日本コスメは機能性成分にも特徴があります。美白や保湿に特化した処方、発酵技術を活かした製品、植物由来のナチュラル成分など、日本の化粧品メーカーが独自に開発した成分や製造技術が「日本品質(J-Quality)」としてブランド化されています。これは特にアジア市場において強力なマーケティング要素となっており、越境ECを通じて商品価値を訴求しやすいポイントです。
デザイン面でも日本の化粧品は高い評価を得ています。シンプルかつ洗練されたパッケージや、使いやすさを追求した容器の工夫などは、欧米市場でも差別化要素として受け入れられやすく、ギフト需要にもつながっています。特にミニマルで清潔感のある外観は、ライフスタイル重視の消費者層に訴求力を持ちます。
さらに、日本発のビューティートレンドにも注目が集まっています。例えば、シートマスクや二層美容液など、アジアで生まれた美容アイテムを日本企業が洗練させて世界に発信する動きが広がっており、越境ECでのヒット商品が生まれる要因ともなっています。
国別では中国市場での人気が特に高く、2020年以降、日本からの化粧品輸出の約半分を中国が占めるほどの規模に成長しています。インバウンド需要との相乗効果もあり、「Jビューティー」の認知が世界中で高まっている今、日本製化粧品を取り扱う越境EC事業は、まさに追い風を受けている状態といえるでしょう。
3-2. 国内市場が縮小している
日本の化粧品市場は長らく安定した成長を続けてきましたが、近年は少子高齢化の進行や人口減少の影響により、需要の伸びが鈍化しています。市場はすでに成熟期に入り、2020年以降の成長率は年2~5%にとどまるなど、今後の大幅な拡大は見込みにくい状況です。特に若年層の人口減少は、トレンドに敏感な顧客層の縮小を意味し、ブランドの成長戦略にも影響を与え始めています。
こうした背景の中、越境ECは新たな成長機会を見出すための有力な手段として注目を集めています。海外、とくに中国や東南アジアなどの新興市場では、化粧品需要が年々拡大しており、日本製コスメへの関心も高まっています。越境ECを活用することで、国内市場の限界を超えて、こうした成長市場の需要を取り込むことが可能になります。
さらに、海外には日本とは異なる顧客層が存在します。例えば、高級スキンケア製品は中国の富裕層に、価格帯が手頃な「プチプラコスメ」は東南アジアの若年層に人気があります。このように、製品ごとに適した市場を選定することで、国内では十分な売上が見込めなかった商品も、新たな活路を得られる可能性があります。
また、日本国内では価格競争が激しく、商品の価値に見合わない価格での販売を強いられることもありますが、海外では「日本製」というブランド価値が通用する場面も多く、適正価格での販売が実現しやすくなります。特にスキンケアや機能性化粧品は高品質なイメージとともに高付加価値商品として認知され、現地消費者に受け入れられています。
加えて、越境ECは製品のライフサイクルを延ばす手段としても有効です。国内で成熟期に入った商品でも、海外では目新しい存在として注目されることがあり、開発投資に対する回収効率を高めることができます。
このように、国内市場の縮小という構造的課題に直面するなかで、越境ECは日本の化粧品メーカーにとって成長と安定を両立させるための戦略的な選択肢となり得ます。海外市場をターゲットとした展開は、中長期的な企業価値の向上にもつながるのです。
3-3. 低コストでの参入が可能
越境ECの大きな魅力のひとつは、初期投資を抑えながら海外市場にチャレンジできる点です。従来のように海外現地に店舗を構えようとすると、物件の賃貸契約や内装工事、現地スタッフの採用・教育など、多額の資本が必要になります。それに対して、越境ECであれば、オンラインストアの構築と物流体制の整備に必要な費用だけで参入が可能で、数十万円からスタートすることも十分に現実的です。
また、越境ECはスモールスタートに適しており、在庫を少量に抑えながらマーケットの反応を確認することができます。たとえば、ある特定の商品カテゴリーだけでショップを開設し、反響に応じて徐々に取り扱い商品を増やしていくといった柔軟な展開が可能です。仮に期待したほどの反応が得られなかったとしても、実店舗に比べて撤退に伴うコストは軽微で、リスクを最小限に抑えられます。
プロモーションにかかるコスト面でも越境ECは有利です。現地店舗では新聞・テレビ・看板広告などの費用が発生しますが、越境ECではSNSやインフルエンサーを活用したマーケティングが主流であり、ターゲットを絞った効率的な集客が可能です。とくにコスメ・化粧品は視覚的な魅力が大きいため、InstagramやTikTokなどのビジュアル重視のSNSとの相性が非常に良く、費用対効果の高い販促手段となります。
さらに、人件費の観点からもメリットがあります。現地に常駐するスタッフを雇う必要はなく、多言語対応は外部の翻訳サービスやツールで補えます。問い合わせへの対応もカスタマーサポート業務をアウトソーシングすることで、国内拠点からでも十分に対応可能です。
実際に、多くの企業がまず越境ECを通じて海外市場でのニーズや価格帯、競合環境などを見極めたうえで、将来的に実店舗を出店するかどうかの判断材料としています。このように、越境ECは少ないコストでグローバル展開への第一歩を踏み出せる、現代的かつ戦略的な選択肢となっています。
4. 越境ECにて化粧品販売を行うことのメリット
4-1. 市場拡大

越境ECによる化粧品販売は、地理的制約を超えて多様な国や地域の市場にアクセスできる、現代ビジネスにおける有力な手法です。特に日本国内の化粧品市場は、少子高齢化や人口減少の影響により飽和状態にあり、今後の大きな成長は見込みにくい状況です。そのような背景の中、国外市場に販路を拡大することは、企業にとって売上の新たな成長源を得る絶好の機会となります。
越境ECを活用すれば、アジア圏の新興国や欧米の成熟市場など、文化や嗜好の異なる幅広い層にリーチ可能です。たとえば、中国の富裕層や東南アジアの若年層、ヨーロッパのナチュラル志向消費者など、日本製化粧品の品質や安全性を評価する層が多数存在しています。これにより、製品の受容者が拡大し、既存市場への依存度を下げながら、売上の多様化と安定化を図ることが可能になります。
また、複数の国・地域で販売実績を持つことで、外部環境の変動に強い事業基盤が築かれます。国ごとの成長ステージや購買力に応じて戦略を柔軟に調整できることは、ビジネスの持続可能性を高める大きな要素です。こうした観点からも、越境ECは今後の企業成長に欠かせないチャネルといえるでしょう。
4-2. 海外へのブランド認知度アップ
越境ECは単なる販路拡大にとどまらず、化粧品ブランドの国際的な認知度を向上させる有力な手段でもあります。オンラインプラットフォームを通じて世界中の消費者に製品を届けることで、自社ブランドのメッセージや世界観を直接伝えることができます。実店舗とは異なり、ブランド側が主導権を持ってコミュニケーションできる点が大きな魅力です。
たとえば、SNSや動画配信サイト、レビューサイトを活用したプロモーションにより、現地の文化やトレンドに合わせた発信が可能です。中国のRED(小紅書)や東南アジアのInstagram、欧米のYouTubeインフルエンサーなどを活用すれば、現地の消費者の共感を得ながら、ブランドロイヤルティを高めることができます。また、これまで国内市場のみで販売されていた製品が、海外の消費者によって「日本ならではの商品」として新鮮に受け取られ、話題化することもあります。これは、ローカルでは埋もれていた商品が、グローバル市場では差別化された魅力として認識されるという現象です。こうしたブランドの再発見や再定義は、越境ECだからこそ実現できる価値の一つといえるでしょう。
4-3. 低リスクで海外進出が可能
越境ECの最大の魅力のひとつは、物理的な制約や大規模な初期投資を伴わずに、比較的低リスクで海外市場に参入できる点にあります。従来型の進出方法では、現地での店舗賃借や人材採用、法人設立などに多額のコストと時間がかかっていましたが、越境ECであればオンライン上で販売チャネルを構築できるため、これらの負担を大幅に削減できます。
特に中小企業やスタートアップにとっては、限られた資金でグローバル市場に挑戦できる点が大きなメリットです。たとえば、在庫も最小限に抑え、反応を見ながら商品ラインや広告施策を柔軟に調整する「スモールスタート」が可能です。これにより、販売実績や顧客の反応を分析しながら、段階的に事業をスケールアップしていくことができます。
さらに、オンライン上の各種データ(アクセス解析、購買履歴、カスタマーレビューなど)を活用することで、現地での需要や嗜好を把握し、商品企画や販促施策にリアルタイムで反映させることが可能です。こうしたデータドリブンな運営体制は、リスクを最小化しつつ最大の効果を得るための強力な武器となります。
5. 越境ECで化粧品販売を行ううえでの注意点

5-1. 法律や制度について
越境ECで化粧品を販売する際は、対象国の法律や規制を遵守することが必須です。多くの国では、化粧品の成分、ラベリング、広告に関して厳格な基準が設けられており、コロナ禍以降は健康・衛生意識の高まりから規制の運用が大きく変わる国も出てきました。特にEUや米国では、特定の成分の使用が制限されており、違反すると重い罰金の徴収や販売禁止措置が課される可能性があります。事業者は、販売を開始する前に、対象市場の化粧品に関する法規制を把握し、適切なアドバイスを受ける準備が不可欠となります。
5-2. 配送時の対応
化粧品の国際配送には、特に注意が必要です。温度変化や湿度が製品の品質に影響を与えるため、適切な梱包材と一定保存条件での発送・輸送が求められます。また、破損を避けるための保護措置も重要で、万一のトラブルに備えた体制づくりも役立ちます。消費者への迅速な配送を保証するためには、信頼できる物流パートナーを選ぶことが大切であり、配送コストと効率のバランスを見極めることも事業の成功に寄与します
5-3. 輸出許可証の申請
多くの国では、特定の化粧品を輸出する際には輸出許可証が必要になることがあります。この手続きでは、製品の成分構成や安全性データの詳細な提出が求められ、対応には時間がかかることもしばしばです。変更が頻繁な市場では、最新情報の収集と早めの申請準備が成功のカギになります。正しく許可を得ておくことで、現地消費者や取引先からの信頼を得ることができます。
5-4. 決済方法のバリエーション
国際的な顧客を対象とする越境ECでは、多様な決済方法を提供することが不可欠です。現地で一般的に使える決済手段に対応していないと、顧客の離脱に繋がるリスクがあります。たとえば、クレジットカードや電子マネー、スマートフォン決済など、国ごとのニーズを反映した選択が必要です。為替レートの変動にも対応した設計にすることで、グローバルな販売展開に柔軟性を持たせることができます。また、決済のセキュリティ面の対策も重要で、顧客の利便性と安全を最優先に考えたシステム構築が求められます。
6. 化粧品販売の際の各国の要件
化粧品を越境ECで販売する際は、国ごとに異なる法制度や規制をしっかりと把握する必要があります。ここでは、中国、アメリカ、ヨーロッパ(EU)それぞれの主要な要件を整理して解説します。
6‑1. 中国の場合
中国向け化粧品の越境ECには、国家薬品監督管理局(NMPA)への登録または届出が必要です。 特殊化粧品(美白・育毛・日焼け止めといった特定機能を謳う製品)は登録が必要であるのに対し、 一般化粧品(保湿・リップなど)は届出のみで済むとされています。手続きの簡素化や名税枠の拡大など、中国の越境ECは全体として規制緩和が推進されているものの、税関の通関審査など、輸入手続きにはなお慎重な対応が求められます
6‑2. アメリカの場合
アメリカで化粧品を販売するには、米国食品医薬品局(FDA)の制度に準拠する必要があります。基本的に化粧品は事前承認なしで販売可能なカテゴリですが、使用禁止成分が明示されており、パッケージにはINCI(国際的成分名称)で成分表示が義務付けられています。また、「治療」「秩序回復」など医薬品的な表現は禁止されており、文言には注意を要します。さらに、2022年に成立したMoCRA(Modernization of Cosmetics Regulation Act)により、製造業者や輸入業者には製品登録・施設登録・成分報告の義務が段階的に導入されています。
6‑3. ヨーロッパ(EU)の場合
EU域内での化粧品販売には、EU化粧品規則(EC 1223/2009)の遵守が不可欠です。まず、EU域内に責任者を設置し、製品の安全性、製品安全報告書、表示内容などの法的対応の責任を担わせる必要があります 。さらに、製品ごとにCPSR作成(安全性評価)とCPNP(EU統合通知ポータル)への事前届出が義務付けられます。また、動物実験の全面禁止が適用され、動物実験済みの製品はEUで販売できません 。
7. 海外進出・海外展開における影響
現代のグローバル化が進む中で、特に越境EC市場は、日本企業にとって顕著な成長機会を提供しています。化粧品業界における海外進出は、ただ単に新たな市場を開拓するだけでなく、ブランドの国際的な認知度を高め、企業の総収益を向上させる可能性を秘めています。この文脈で、海外市場への進出を考える際の重要な要素として、電子決済の普及と消費者のオープンマインドな購買行動が挙げられます。日本と比較して、多くの国々ではECでのショッピングが日常化しており、特にデジタル決済が広く浸透しています。このような市場環境は、日本企業が新たな顧客層にリーチしやすくなるため、積極的に利用すべきです。
化粧品の越境EC展開において、ターゲット市場の選定は訪日外国人観光客の動向から有益な洞察を得ることが可能です。訪日観光客の出身国と彼らが関心を寄せる製品を調査し、データをまとめることで、どの地域に市場の機会が潜んでいるかを見極めることができます。特に中国、韓国、台湾からの観光客が日本のスキンケアや化粧品に対して顕著な興味を示しているため、これらの地域は越境EC展開のための理想的な初期市場と言えます。
また、中国市場の隆盛に続き、東南アジア諸国も急速に成長している市場として注目されています。フィリピン、マレーシア、タイ、ベトナムといった国々では、日本のかつての高度経済成長を彷彿とさせるような経済発展を遂げており、消費者の購買力も向上しています。これらの国々では、特に中産階級の台頭と美容への意識の向上が見られ、高品質な日本製化粧品への需要が増大しています。これらの市場のデジタル化が進展しており、オンラインショッピングが普及していることから、越境ECを利用した販売戦略は特に効果的です。
海外市場への進出を成功させるためには、これらの市場の文化や消費者行動を理解し、地域に適したマーケティング戦略を展開することが重要です。デジタルマーケティング、特にソーシャルメディアを活用したプロモーションや、地域ごとにカスタマイズされた製品提供が成功の鍵となります。さらに、法規制の遵守、適切な物流戦略、多様な決済オプションの提供など、細部にわたる配慮が求められるため、これらの点に留意しながら計画的に事業を展開していくことが求められます。
以上のように、海外市場への進出は多大な努力と戦略的な計画が必要ですが、それに見合うだけの大きなリターンを企業にもたらす可能性を秘めています。日本企業が国際市場で競争力を持ち、持続可能な成長を遂げるために、グローバルな視点を持って取り組むとよいでしょう。