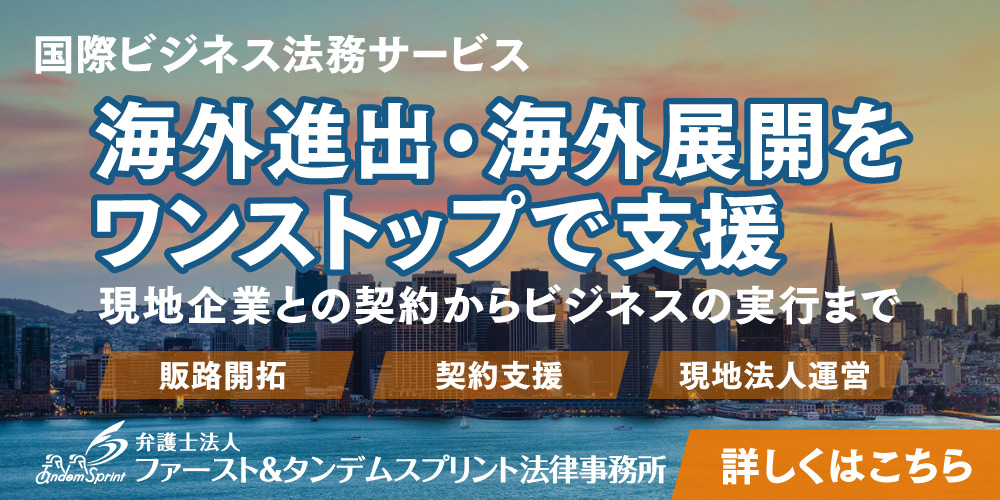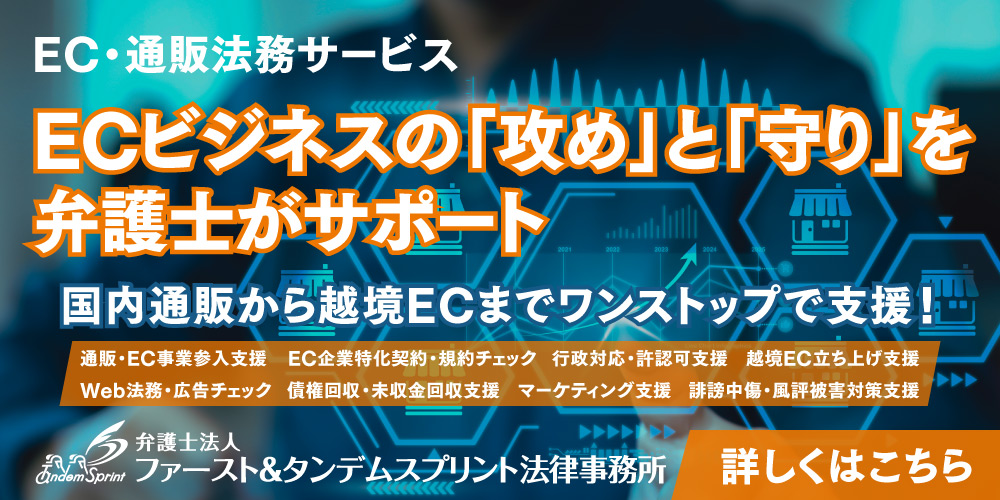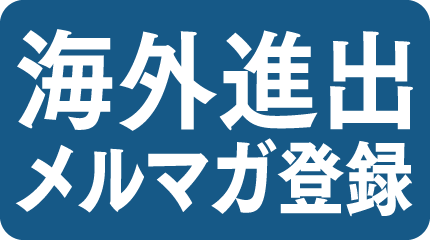目次
越境ECの市場規模と今後の動向

近年、越境EC(電子商取引)は世界中で急速に拡大しています。特に日本を含むアジア市場やアメリカ、ヨーロッパなどの国々では、越境ECを活用する企業が増加し、消費者にも大きな魅力を持っています。国内ECと越境ECの違いとして、言語や通貨、法律などの対応が必要になる一方で、新たな市場に出店できる点が大きなメリットです。2024年を迎え、越境EC市場の規模はますます膨らみ、今後も成長を続けると予測されています。本記事では、越境ECの市場規模や今後の動向、人気の越境ECサイトランキング、そしてプラットフォーム選定のポイントまでを徹底解説します。
越境EC市場は、2021年に約7,850億米ドルと評価され、2022年から2023年にかけて大きく成長し、世界全体の取引規模は数兆円規模に到達すると推定されており、2030年までに7.9兆米ドルに達すると予測されています。特に中国、アメリカ、日本、ヨーロッパ圏の国際間取引が活発であり、BtoCおよびCtoCプラットフォームを通じた販売が年々増加しており、別のチャネルでの展開や販売戦略の多様化も進んでいます。また、日本企業による日本製の品物の人気が高まっています。日本ブランドは、その品質の高さと安全性により、海外の中間層や富裕層の人々に信頼されています。
2024年時点では、スマートフォンの普及、利用者の増加、SNS経由の購買行動、多言語対応ECサイトの拡充などにより、越境ECの参入障壁が下がってきており、中小企業や個人事業者でも参入しやすい環境が整ってきました。
加えて、越境EC支援サービスの普及や物流・決済インフラの整備が進んだことで、海外への販売や購入がよりスムーズになっています。JD(京東/JD.com)などの大手中国ECサイトは、その機能の豊富さや利便性で注目されています。特にアジアでは日本製品への信頼が高く、健康食品、化粧品、家電などの日本ブランドが強みを発揮しています。
今後2025年に向けては、以下のような動きが予測されています:
・地域別対応の深化(現地配送・カスタマーサービス強化):現地配送やカスタマーサービスの強化が進むと予想されます。
・AIを活用したマーケティングと商品レコメンドの導入:パーソナライズされた購買体験の提供が重要となります。
・新興国市場(東南アジア・南米)への拡大:これらの地域での市場開拓が進むと見られます。
越境ECプラットフォーム間での競争が激化するなか、企業は市場調査、現地規制対応、言語対応など、戦略的な取り組みが求められます。これらの理由から、どのプラットフォームに出店するかは非常に重要です。
越境ECサイトの人気ランキング

越境ECサイトは、各国のユーザー(消費者)に向けて様々な商品やサービスを提供しています。ここでは、世界全体と地域別における人気の越境ECサイトをランキング形式で紹介し、それぞれの特徴や活用事例、構築に役立つ資料もあわせて解説します。
全世界ランキング
1 Amazon(アメリカ)
世界最大のオンライン小売業者であり、国際的な取引規模を誇ります。日本をはじめ、ヨーロッパ、アジアの市場にも強い影響力を持ち、EC市場で非常に高いシェア率を占めています。多くの国のユーザーにとって、最も信頼されているプラットフォームの一つです。
2 AliExpress(中国)
中国の大手企業アリババが運営する越境ECサイト。価格の安さと商品バリエーションの多さから、多くのユーザーに人気。特にガジェットや日用品の販売に強く、新興国市場を中心に高い利用率を誇ります。物流網の構築にも力を入れており、配送の速さにも定評があります。
3 eBay(アメリカ)
オークション形式や即売形式が特徴で、中古品・レア商品の出品も多く、コアなファンに支持されています。アメリカ・ヨーロッパでの取引事例も多く、特に個人事業主や小規模企業向けに適した販売チャネルです。
*注意点
データの変動: オンラインマーケットプレイスのランキングや市場シェアは、調査機関や評価基準によって異なる場合があります。最新の情報を確認する際には、複数の信頼できる情報源を参照することが重要です。
株式会社リソース・シェアリング
地域特性: 各プラットフォームの人気やシェアは、地域や国によって異なります。ターゲット市場に応じて、適切なプラットフォームを選択することが成功の鍵となります。
以上の情報を踏まえ、越境EC戦略を検討される際には、最新の市場動向や各プラットフォームの特性を十分に理解し、適切な選択を行うことをおすすめします。
地域別ランキングと関連情報
中国市場:価格競争力と物流効率が鍵
主要プラットフォーム:AliExpress、Tmall Global、JD Worldwide
中国では依然として「AliExpress」が高い人気を誇り、コストパフォーマンス重視のユーザー層を中心に広く利用されています。加えて、アリババグループ傘下の「Tmall Global(天猫国際)」や、「JD Worldwide(京東国際)」も越境ECの主要チャネルとして台頭しています。1位の座を維持し続ける「AliExpress」は、中国国外への商品販売も活発です。越境ECの関連施策として、物流・関税対応の最適化が進んでおり、日本の事業者にとっても進出価値のある市場です。
特徴と戦略:
・「Tmall Global」はプレミアム志向で、ブランド力を持つ日本企業に向いています。
・「JD」は自社物流を持ち、配送スピードや信頼性が高く、家電や日用品に強み。
・日本製品は「品質」「安全性」「信頼性」が評価されており、特に健康食品やスキンケア用品の需要が高いです。
注意点:
・税制度が頻繁に改定されるため、出店時は関税・消費税・行郵税に関する最新情報の把握が必須。
・プラットフォーム上の出店審査が厳格で、公式代理店との連携や出店支援会社の活用がスムーズ。
ヨーロッパ市場:ファッション・サステナブル志向に注目
主要プラットフォーム:Zalando(ドイツ)、ASOS(英国)、Cdiscount(フランス)
欧州市場では「Zalando」「ASOS」などがファッション領域で高い支持を集めており、デザイン性・ストーリーテリング性のあるブランドに適した環境です。ファッション分野での成功事例が多く、デザイン性の高い日本ブランドとの親和性も高いため、出品を検討する価値は十分です。特にZalandoは、ヨーロッパ全域への流通網を持ち、EU加盟国内での物流対応が効率的です。
特徴と戦略:
・エコ・サステナブル関連のトレンドが強く、日本の伝統工芸や素材にこだわった商品が受け入れられやすい。
・EU圏内に拠点を置くことで、VAT制度(付加価値税)への対応がしやすくなる。
・「Made in Japan」の信頼性が高く、別注(カスタム)品や数量限定の展開にも相性が良い。
注意点:
・国ごとに文化・言語が異なるため、ローカライズ対応が不可欠。
・商品の返品ポリシーが厳格な国も多く、返品送料や対応体制の整備が必要。
アメリカ市場:差別化と「人」軸のブランド構築が鍵
主要プラットフォーム:Amazon、Etsy、Walmart、Shopify
アメリカでは「Amazon」の圧倒的なシェアは変わらないものの、「Etsy」「Walmart」も注目されており、特にユニークさやストーリーを重視するマーケットが形成されています。個人や小規模事業者も多数参加しており、「人」や「想い」を売るブランディング戦略が有効です。特に「Etsy」は独自性や手作りの魅力を打ち出すブランドに適しており、ユーザー層とのマッチング率も高く、差別化された戦略での構築が求められます。
特徴と戦略:
・Etsyは「手作り」「ヴィンテージ」「アート」系のプロダクトに強く、日本の工芸品やオリジナル雑貨が人気。
・Amazon.comではFBA(Fulfillment by Amazon)を活用することで、現地配送・顧客対応の手間を軽減可能。
・Shopifyを使ったD2C型ブランドも拡大中。自社ECで自由なデザイン・マーケ戦略を展開できる。
注意点:
・「消費者レビュー文化」が強いため、配送遅延や説明不足への反応が厳しい。
・プライバシー・知的財産に関する法規制(CCPAなど)への対応も考慮が必要。
補足:新興国・東南アジア市場も成長中
注目プラットフォーム:Lazada(東南アジア)、Shopee(台湾・ASEAN)、Mercado Libre(南米)
人口増加とスマホ普及により、インドネシア・ベトナム・フィリピンなどのASEAN諸国や、ブラジル・メキシコなどの中南米でもEC市場が急成長しています。
・Lazada/Shopeeは、現地言語対応とローカル物流を提供し、日本企業のテスト販売にも適したプラットフォーム。
・中価格帯〜廉価帯の商品が好まれるため、商品選定・価格戦略がカギ。
・日本ブランドへの信頼感も根強く、「安心・高品質」の価値訴求が効果的。
※ここで紹介したランキングやシェア率は、2023年〜2024年時点の調査結果をもとに作成されています。2025年以降の市場動向に合わせたアップデートにもご注目ください。
プラットフォームを選択する際のポイント

越境ECサイトを選ぶ際には、以下のポイントを考慮することが重要です。適切な選定は継続的な売上獲得に寄与し、購入率の向上やSEO対策となります。
・ターゲット市場の特定
どの地域の消費者に向けて販売するかを明確にし、その市場に適したプラットフォームを選びましょう。例えば、アメリカやヨーロッパ市場ではAmazonやeBayが有名ですが、中国市場ではAliExpressが優位です。国によって需要のある製品ジャンルや価格帯が異なるため、一定の調査が必要です。
・商品ジャンルの確認
扱う商品(製品)に適したECサイトを選ぶことも重要です。ファッションや美容関連なら「Zalando」や「ASOS」などの専門サイトが効果的です。出品したい商品がどのカテゴリに強いかを調べ、関連コンテンツやレビューの充実度も比較ポイントとなります。
・配送と支払い方法
海外配送が可能であること、そして消費者にとって便利な支払い方法を提供することが、越境EC成功の鍵です。柔軟な配送設定や多通貨決済への対応は、ユーザー利用のしやすさに直結します。
・サイト構築・運営の選択肢
自社の商品やターゲット市場に合わせたプラットフォーム選定が重要です。例えば、ShopifyやWooCommerceのようなCMSを活用すれば、独自サイト構築が可能で、出品一覧ページの最適化やSEOコンテンツの運用もしやすくなります。自社ECサイトの運営はブランディングや長期的な顧客獲得にもつながります。
・サポートと実績のある会社を選ぶ
導入支援や翻訳対応、現地マーケティングまでカバーしてくれる会社と連携することで、運営初期の不安を軽減できます。資料請求や導入事例を比較しながら、自社に合ったパートナーを見極めましょう。
このように、戦略的なプラットフォーム選定によって、売上やユーザー体験を一定以上の水準に保つことができます。成功事例を参考に、最適な構築と出品戦略を立てましょう。
上記で示した通り、それぞれのプラットフォームには機能面での違いがあり、選ぶ際には「販売したい品のジャンル」「ターゲットとなる人」「配送・決済の手間」「国内外の物流体制」などを考慮することが重要です。例えば、分かりやすく以下のように考えるのも良いかもしれません。
・健康食品や化粧品 → JD.com、Tmall Global
・コレクター向け商品や中古品 → eBay
・幅広いカテゴリーで効率よく売りたい場合 → Amazon Global
・新興市場でのブランディングを目指す場合 → Shopee
また、国内の在庫を活かして出荷できるか、または現地倉庫を使うかによっても戦略が変わります。利便性やサポート体制を重視する日本企業には、日本語対応が整った楽天グローバルやAmazonが特におすすめです。
越境ECを成功させるには、適切なプラットフォームの選定がカギとなります。2024年現在で特に人気のあるプラットフォームを、日本企業や個人出店者向けに以下の一覧で比較し紹介していきます。

越境EC事業を行う際の注意点

越境ECを運営する際には、以下の点に注意する必要があります。それぞれのリスクや対応策を項目ごとに把握し、事前にまとめておくことが、安定した運営につながります。
1.税関手続きと関税
国際取引では必ず税関を通過し、国によっては関税や付加価値税(VAT)が徴収される場合があります。これに関する制度は国ごとに異なるため、商品の発送一覧や配送ルールを整理し、適切な対応を行うことが求められます。
2.消費者保護法の理解
各国の消費者保護法に準拠することが不可欠です。特に返品・交換ポリシーや商品説明については、法律に適合した表現を用いる必要があります。主要国の規制をまとめた資料を用意しておくと便利です。
3.多言語対応
各国の消費者に対応するには、言語や文化に配慮した商品説明やカスタマーサポートが必要です。翻訳精度の高いツールや現地スタッフの協力が鍵になります。
上記のポイントをさらに掘り下げて、背景、リスク、具体的対応策、国内と越境の違いを盛り込み、出店者や日本企業にとって実践的な内容を解説していきます。
1.税関手続きと関税の正確な理解
背景:
越境ECでは、どの国への販売であっても通関というプロセスを通る必要があります。輸出入の際に適用される関税やVAT(付加価値税)は国によって大きく異なり、商品カテゴリや価格帯によって課税額も変わるため注意が必要です。
主なリスク:
・購入者が思わぬ関税負担を強いられてトラブルに発展
・書類不備により通関で商品が止まり、配送が大幅に遅延
・関税が価格に上乗せされ競争力が低下
対応策:
・主要取引国(例:中国、アメリカ、EU諸国)の税制度を事前調査
・HSコード(品目分類)を正確に把握し、商品別の関税率をリスト化
・DDP(関税込込)/DAP(関税別)いずれで販売するか明示する
・税関書類(インボイス、納品書)のテンプレートを国内で整備
・自社倉庫 or フルフィルメントセンター(FBA/JD倉庫)を使って手続きを簡素化
2.消費者保護法の理解とローカルルールの順守
背景:
各国の消費者保護法には返品期間、品質保証、表記方法、表示義務などの規定があり、国内基準とは異なるケースが多く見られます。日本の感覚で運営すると、思わぬクレームや違反と見なされることがあります。
主なリスク:
・法令違反でアカウント停止や罰金を科せられる
・消費者トラブルがSNSで拡散しブランド毀損
・商品説明不足で返品率増加
対応策:
・主要販売国の消費者保護ルール(返品期限、送料負担、表記義務)を比較表にして社内共有
・特に欧州(GDPR含む)や米国(FTC)では厳格な表記ルールあり、事前の翻訳チェックが必須
・返品ポリシーは多言語で明示、紛争解決プロセスもセットで説明
・国ごとのFAQ・利用規約のテンプレートを用意する
3.多言語対応とローカライズ
背景:
世界のユーザーに商品を届けるには、言語だけでなく文化・習慣も意識したローカライズが重要です。ただ翻訳するだけでは信頼を得ることはできません。
主なリスク:
・機械翻訳による誤訳で誤解やクレーム発生
・文化にそぐわない表現が不快感を与える
・カスタマー対応に時間がかかり機会損失
対応策:
・商品説明文・タイトルは機械翻訳+人のチェックで精度向上
・ネイティブスタッフや翻訳会社との連携(特にJDやTmallは現地仕様が厳格)
・カスタマー対応には多言語チャットツール(例:Zendesk, Intercom)の導入
・中華圏、東南アジア、欧州など地域別のカスタマー対応テンプレを用意
その他にも注意すべき点
・決済手段の多様化:地域に応じてAlipay、WeChat Pay、PayPal、Klarnaなどが主流。国内とは違う決済ニーズを理解し、利便性を担保することが重要です。
・配送遅延リスク:国際物流は天候・通関・政治リスクにより遅れることも。あらかじめ到着日数に幅を持たせる表記と、配送状況の追跡機能を設けることが信頼に繋がります。
・知的財産権の管理:海外では模倣品も多く出回るため、商標・著作権の国際出願や、プラットフォーム上での模倣対策(Tmall/JDのブランド保護登録)も必要です。
これらの注意点は、越境ECを安定して運営するために不可欠な視点です。税関対応、法規制、言語サポート、物流や決済など、国内とは異なる課題が複雑に絡み合うのが越境ECの特徴です。加えて、国や地域によって求められる条件や消費者の期待も異なるため、単に商品を海外に出すだけでは成果は上がりません。
事業者はこれらのリスクを正しく認識し、早い段階から必要な対策を講じることが、トラブルを未然に防ぎ、信頼を積み上げることに繋がります。
越境EC事業に関するお悩みは専門家にご相談ください

越境ECは魅力的なビジネスチャンスを提供しますが、運営には一定以上の専門的知識と準備が必要です。市場調査、物流、関税、消費者法など複数の分野にまたがるため、これらを一覧で把握できるよう、専門家と連携するのが安心です。
越境ECの市場は急速に進化しており、2025年に向けてさらに多くの企業が参入すると予測されています。事業者としては、今後の動向を注視しながら、適切なプラットフォーム選定とマーケティング戦略の構築・まとめを行うことが、成功のカギとなります。