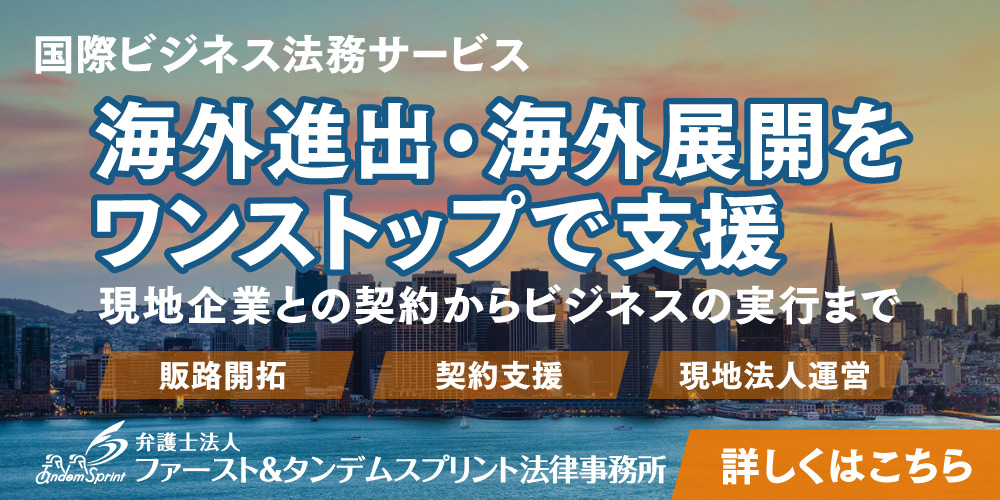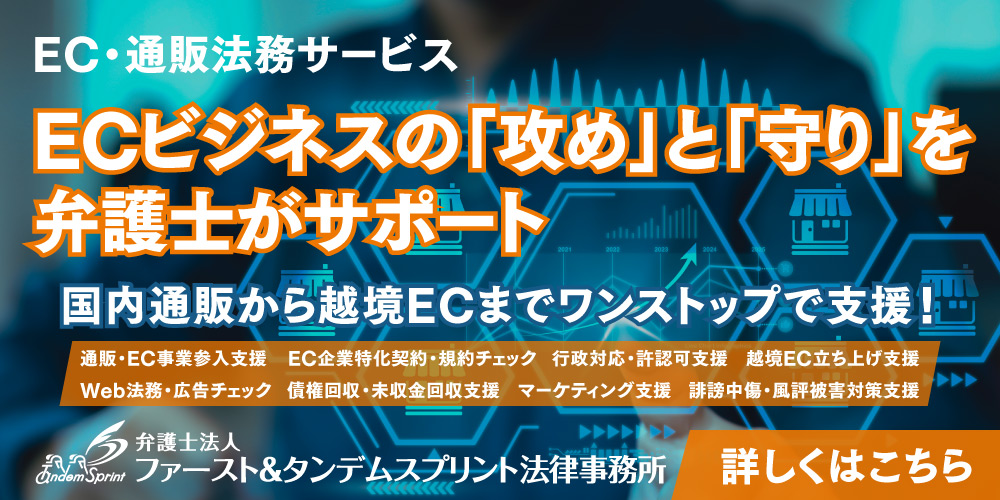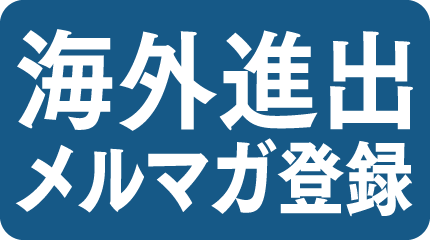目次
1.越境ECとは

日本から海外へ:なぜ今、越境ECが注目されるのか
越境EC(Cross-border E-Commerce)とは、国や地域を越えて、インターネット上で商品やサービスを売買する取引形態を指します。たとえば、日本の個人事業主がアメリカの消費者にオンラインで自作の雑貨を販売するようなケースがこれにあたります。ECは「Electronic Commerce(電子商取引)」の略であり、それに「越境」という要素が加わることで、国内にとどまらずグローバル市場を対象としたインターネット販売という意味になります。
近年、この越境EC市場は急速に成長しており、特にアジアや北米、欧州を中心に国境を超えたオンラインショッピングが一般化しつつあります。多くの調査資料でも、越境ECの市場規模が今後も拡大傾向にあることが明らかにされており、特にアジア圏ではスマートフォン普及率の高さや越境対応プラットフォームの利用増加が成長を後押ししています。Amazon、Shopify、eBayなどのグローバルなEC基盤の整備に加え、SNSを通じたマーケティング手法の進化もこの傾向に拍車をかけています。
日本国内においても、コロナ禍を契機としたオンライン化の加速や、国内市場の人口減少による購買力の鈍化により、海外市場に目を向ける企業・個人が増加しています。特に、Made in Japanブランドへの信頼性や、日本製品特有の品質・デザインへの人気が根強い地域(東アジア、東南アジア、北米など)では、日本からの越境ECがビジネスチャンスとして大きく広がっています。
また、以前は法人でなければ越境ビジネスを始めにくいという印象がありましたが、最近では個人でも比較的簡単に始められる環境が整ってきたこともポイントです。たとえば、越境EC対応のネットショップ構築ツール(Shopify、BASE、STORESなど)を活用すれば、英語表記のオンラインストアや多通貨決済、海外配送にも対応可能です。さらには、PrintfulやBuyee、ZenMarketといった越境ECをサポートする外部サービスの利用により、在庫リスクを持たずに「受注→製造→発送」までを一貫して外部委託する仕組みも一般的になっています。
越境ECを始めるにあたっては、最新の資料を参考にしながら、自社や個人の強みをどの市場にどう活かすかを検討することが、成功への第一歩となるでしょう。
越境ECの代表的な販売モデル
越境ECといっても、いくつかの形態があります。代表的なモデルは以下の通りです。
・自社サイト型(例:Shopify、BASEなど):
オリジナルブランドを立ち上げたい場合や、自分でマーケティングやサイトデザインをコントロールしたい場合に適しています。
顧客との直接的な関係構築が可能。
・マーケットプレイス型(例:Amazon、eBay、Etsyなど)
すでに集客力のあるプラットフォームを利用でき、すぐに販売開始しやすい点が魅力。
競合も多く、価格競争に巻き込まれることも。
・代理購入型・転送型(例:Buyee、ZenMarketなど)
日本語サイトで販売した商品を、海外ユーザーが代理購入してくれる形。
販売者自身は海外発送やカスタマー対応をしなくて済むのが特徴。
それぞれのモデルには一長一短がありますが、個人で初めて越境ECを始める場合は、手数料や対応範囲を含めてどのモデルが自分の商材や運営スタイルに合っているかを見極めることが重要です。
越境ECに必要な対応とは
越境ECでは、単に「海外に向けて商品を売る」というだけでは済まず、以下のような対応が求められます。
・多言語対応(特に英語)
・複数通貨での決済手段の整備
・国際物流手段の選定と発送対応
・現地の消費者保護法や輸出入規制の確認
・返品・返金ポリシーの策定
・カスタマーサポート体制の確保
特に「商品の発送」と「トラブル対応」は、国内ECよりもはるかに複雑になります。商品が届かない、関税が発生した、海外の消費者と連絡が取れないといったトラブルも想定し、信頼できる物流業者や外部サポートの導入が鍵となります。
越境ECは、国際的な販売チャネルを手軽に持てる可能性を秘めたビジネスモデルですが、その反面、法律・物流・言語といった複数の壁を乗り越える必要があります。本記事では、そうした課題を乗り越えるために、個人で越境ECを運営するメリットとデメリットについて解説していきます。
2.個人で越境ECを運営するメリット

個人で越境ECを始めるというと、「法人じゃないと難しそう」「海外発送は手間がかかりそう」といった不安を持つ方も多いかもしれません。しかし、現在ではECプラットフォームや物流・決済サービスの進化により、個人でも海外に向けてスムーズに商品を販売できる時代になっています。むしろ、法人にはない柔軟性やコストの低さを活かし、個人ならではのアプローチでグローバル市場にチャレンジすることが可能です。
以下では、個人が越境ECを運営するメリットについて、具体例を交えながらご紹介します。
小資本から始められる
個人で越境ECを始める最大のメリットは、初期投資を抑えたままグローバル市場にアクセスできるという点です。例えば、ShopifyやBASEといったネットショップ作成サービスでは、月額数千円程度から独自のオンラインストアを開設することができます。また、会社を設立せずに個人の立場でも始められるため、副業としてのスタートにも適しています。
さらに、在庫を持たずに商品販売ができる「プリント・オン・デマンド」や「ドロップシッピング」といったビジネスモデルを活用すれば、仕入れや在庫管理のリスクを最小限に抑えることも可能です。たとえば、Tシャツや雑貨などのオリジナルグッズを、Printfulのような外部サービスで受注生産・発送してもらう形にすれば、自分は商品企画とデザインに集中するだけで済みます。
このように、小規模でも効率的にグローバル展開をスタートできるのが、個人越境ECの大きな強みです。
ニッチ市場を狙いやすい
個人の強みは、自分の得意分野や興味を活かして、ニッチなマーケットに特化できることです。法人の場合、大規模なマーケティングや大量生産を前提とした商品展開が求められがちですが、個人は小ロット・少量多品種でも勝負できます。
例えば、「和柄のハンドメイド文房具」「日本の伝統工芸を取り入れた雑貨」「アニメ風デザインのスマホケース」など、海外では手に入りにくいが一定の需要がある商品を扱うことで、熱心なファン層を獲得できる可能性があります。日本文化や美意識への関心が高い北米・欧州・東南アジア圏では、個性ある商品に対する評価が高く、価格よりも独自性や品質を重視する顧客層にリーチしやすい点も魅力です。
自分のブランドを世界に発信できる
個人越境ECでは、自分の趣味やアイデアから生まれた商品を、「自分のブランド」として世界に発信できるという点も見逃せません。従来のように仲介業者や小売店に依存することなく、SNS(Instagram、TikTok、YouTubeなど)を活用しながら、海外の顧客と直接つながれる時代になっています。近年では、無料で使えるSNSツールや越境ECプラットフォームの登場により、個人でも手軽に海外販売を始めることが可能になりました。
たとえば、日本在住のある個人クリエイターが、自作の水彩画をプリントしたポスターや雑貨を販売し、Instagramを通じて北欧やアメリカのファンから注文を受けるようになった事例があります。このように、個人のアートやデザインがSNS経由で「バズり」、越境ECを通じて収益化されるケースは年々増加しています。中国などアジア圏でも、日本人クリエイターの作品が注目されることがあり、検索や情報拡散を通じてブランドが一気に拡大する可能性もあります。
個人であるからこそ、大企業にはない人間味やストーリー性が海外顧客の心を動かすことも多く、自分の発信力と商品力が合致すれば、大きなチャンスが広がります。越境ECのスタートには、まず必要な情報を集め、無料で始められるツールや販路をうまく活用することが成功の鍵となるでしょう。
場所や時間にとらわれない自由な働き方が可能
越境ECはインターネットを活用したビジネスであるため、在宅でも、地方に住んでいても、海外にいても運営が可能です。海外顧客向けに販売していても、インフラさえ整っていれば、日本国内からでも全く問題なく運営できます。副業として始める方も多く、本業を持ちながら空き時間に商品登録・対応を行うというスタイルも十分に可能です。
また、自動翻訳やチャットボット、注文管理ツールなどのサポートツールも充実しているため、少人数で効率的に運営できる環境が整っているのもポイントです。
このように、個人で越境ECを運営することには、コスト面・柔軟性・独自性・自由度といった多くのメリットがあります。もちろん、次章で紹介するように注意点や課題もありますが、しっかりと準備をすれば、自分のアイデアや情熱を世界に届け、収益化につなげることが可能です。
3.個人で越境ECを運営するデメリット

個人で越境ECを始めることには多くのメリットがありますが、その一方で注意すべきデメリットやリスクも存在します。特に個人事業主としての立場では、法人に比べてリソースや法務・税務面の対応に制約があるため、事前にデメリットを把握し、対策を講じておくことが重要です。
ここでは、個人で越境ECを運営する際に直面しやすい主な課題を具体的に解説します。
言語・文化・時差の壁による顧客対応の難しさ
越境ECは、異なる言語・文化・生活習慣を持つ顧客とのコミュニケーションが必要不可欠です。英語をはじめとする外国語での商品説明、カスタマーサポート、トラブル対応などは、多くの日本人にとって大きなハードルとなります。
例えば、「サイズが合わなかった」「商品が届かない」といったクレームを英語で受けた場合、適切かつ迅速に対応できなければ、悪いレビューや返金要求につながり、ブランドイメージに大きなダメージを与えることもあります。また、時差の関係で深夜に問い合わせが来るケースも多く、個人で対応するには限界がある場面も出てきます。
ツールを活用して翻訳や自動返信を設定することも可能ですが、文化的なニュアンスや信頼関係の構築には人間らしい対応が求められることも多く、運営負担は決して小さくありません。
税務・法務の複雑さ
個人であっても、越境ECを通じて海外に商品を販売する以上、輸出に関わる税務や法務の知識が必要になります。国によって異なる輸入関税・消費税・VAT(付加価値税)などへの対応は煩雑で、無申告や処理ミスがあると後にペナルティや追加請求が発生するリスクもあります。
また、2023年以降はEUやアメリカなどで越境ECに対する税務監視が厳格化しており、一定額を超える取引には現地での登録や納税義務が生じるケースもあります。個人ではこれらの制度を理解しきれず、知らないうちに違法行為になってしまう危険性もあります。
たとえば、アメリカでは州ごとにSales Tax(売上税)の取り扱いが異なるため、一定の売上や取引件数を超えると「Nexus(課税義務)」が発生することがあります。こうした制度に対応するには、専門家のサポートや外部ツールの導入が必要となり、個人としての運営コストが増加する可能性があります。
集客の難しさと競争の激化
越境ECの市場は年々拡大しており、とくに中国をはじめとするアジア地域での需要も高まっていますが、その分競争も激化しているのが現状です。大手ブランドだけでなく、他の個人セラーや小規模事業者も多数参入しており、商品の差別化や集客はますます難しくなっています。
SNSを活用したプロモーションに加え、Facebook広告やGoogle広告といったオンライン広告の運用、さらには検索エンジン対策(SEO)も重要になっており、個人が限られた知識や予算の中で対応するには限界があるのも事実です。特に、言語や現地消費者の嗜好、たとえば中国市場特有の購買心理などに合わせたマーケティングは高度な専門性が求められ、期待通りの成果が出せずに悩むケースも少なくありません。
さらに、Amazon Global、Etsy、Shopeeなどの越境ECモールに出店する際も、レビュー数や配送スピード、販売実績といった検索結果での表示順位が影響するため、信頼を得るまでに一定の時間と労力を要する点にも注意が必要です。
返品・配送・トラブル対応の手間
個人で越境ECを運営する場合、物流のトラブルに関する対応を自分で行わなければならないという点も大きなデメリットです。国際配送では、紛失・遅延・破損などのリスクが国内より高く、顧客対応や保険申請、再発送に伴う料金負担など、時間的にも金銭的にも大きなコストが発生する可能性があります。
また、国や地域によっては返品制度が法律で定められており、返品や返金への対応を適切に提供する必要があります。その際、送料の負担や返品商品の再販不可といった要素により、利益率が圧迫されるリスクも考慮しなければなりません。
このように、越境ECの運営は「販売して終わり」ではなく、販売後の対応も含めて責任が伴うビジネスです。個人で行うには、物流、カスタマーサービス、料金管理など多方面にわたる業務を一手に担う必要があり、物理的・精神的な負荷がかかるケースも多く見られます。
デメリットを理解したうえで準備を
個人で越境ECを運営するには、多くの可能性がある一方で、対応すべき課題やリスクも現実的に存在します。言語・法律・集客・物流といったあらゆる側面において、事前の調査と準備が不可欠です。これらのデメリットを理解したうえで、外部ツールや専門家の支援をうまく活用し、無理なく始める体制を整えることが成功への第一歩となります。
4.個人で越境ECを始める際の手順

越境ECを個人で始めるにあたっては、海外販売ならではの準備や手続きが必要です。以下に、初心者でも無理なく取り組める一般的なステップを整理してご紹介します。
1.取り扱う商品を決める
まずは「何を売るか」を明確にすることが出発点です。日本製の商品は品質やデザインに定評があるため、アパレル、雑貨、文具、化粧品、アニメグッズ、伝統工芸品などが人気です。すでに手元にある在庫を活用してスタートするのも一つの方法です。
販売先となる国や地域のニーズ・文化に合っているか、関税・輸出入規制の対象でないかも事前に確認しましょう。
2.販売チャネルを選ぶ
越境ECには大きく分けて、越境ECモールを利用する方法と、自社ECサイトを構築する方法の2種類があります。個人で始める場合は、Amazon Global、eBay、Etsy、Shopee、Shopifyなどのプラットフォームを利用するのが一般的です。
各プラットフォームには手数料や利用規約があるため、商品の特性や販売対象国に応じて最適なものを選びましょう。
3.商品ページの作成
販売プラットフォームを決めたら、次は商品登録です。ここでは、外国語(主に英語)での説明文、サイズ・素材・使用方法などの明記、魅力的な商品画像を用意することが重要です。
翻訳ツールの利用も可能ですが、正確さや信頼性を担保するためにプロの翻訳者やネイティブによるチェックを検討するのも有効です。
4.決済方法と配送手段の設定
海外の顧客がスムーズに購入できるよう、クレジットカード、PayPal、Apple Payなど国際的に対応した決済方法を整備します。多くのモールではすでに決済機能が備わっているため、設定するだけで使える場合がほとんどです。
配送については、日本郵便の国際eパケットやEMS、FedEx、DHLなどの国際配送サービスを活用するのが一般的です。送料や配送時間は顧客満足度に直結するため、分かりやすく提示することが大切です。
5.法務・税務面の確認
販売対象国や商材によっては、輸出・輸入に関する規制や許認可が関係する場合があります。また、現地での納税義務にも注意が必要です。特にEU圏ではVAT登録が求められることもあり、一定の売上を超えた場合は手続きが必要になります。
不安な場合は、国際法務や税務に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
5.個人で越境ECを運営する際の注意点

個人で越境ECを運営する場合、国内ECにはない独自のリスクや課題に直面することがあります。安定した運営と顧客満足度の向上を実現するためには、以下のような注意点を事前に理解し、対策を講じておくことが重要です。
言語と文化の違いに注意
海外の顧客と取引を行う以上、言語や文化の壁は避けて通れません。商品説明やカスタマー対応は基本的に英語で行うことが多く、表現の曖昧さや翻訳ミスがトラブルの原因になることもあります。また、宗教的・文化的な背景により、特定の商品が敬遠されることもあります。
言葉のニュアンスや習慣の違いを理解したうえで、丁寧で明確なコミュニケーションを心がけましょう。FAQや返品ポリシーを英語で整備しておくことも有効です。
配送・関税トラブルのリスク
海外配送では、遅延、破損、紛失といったリスクが常につきまといます。国によっては通関に時間がかかる場合もあり、配送日数が予想以上に伸びることもあります。また、商品によっては現地で関税や輸入消費税が発生し、顧客に追加請求されるケースもあります。
発送前に「関税は購入者負担」といった条件を明記したり、トラッキング付きの配送手段を選んだりするなど、リスクを最小限に抑える工夫が必要です。
為替リスクと決済手数料
海外通貨での取引では、為替変動による収益への影響や、PayPalなどの決済サービスを通じた際の為替手数料・送金手数料が発生します。特に、円安が進んだ場合には手元に残る利益が目減りする可能性があるため、収益管理には注意が必要です。
価格設定の際には為替リスクを加味し、定期的に見直しを行いましょう。
海外マーケットの法規制への対応
販売する商品によっては、販売国の法規制や輸入禁止品目に該当する場合があるため注意が必要です。たとえば、化粧品・医薬品・食品などは、国によっては厳格な認可制度が設けられており、認可を得ずに販売した場合、重大な法的リスクを伴う可能性があります。また、欧州向けの商品にはCEマーキングが、米国向けの商品にはFDA(米国食品医薬品局)の承認が求められるケースも少なくありません。
特に「売れ筋」となる人気カテゴリの商品ほど規制の対象になりやすいため、販売前に十分なリサーチを行いましょう。販売先の法規制や必要な書類、ラベル表示などのルールを確認し、不明点があれば専門家に相談することが重要です。
6.越境EC事業に関するお悩みは専門家にご相談ください

越境ECは、個人でも「海外向け」にビジネスを展開できる大きなチャンスをもたらします。しかしその一方で、言語の壁や法律・税制の違い、物流や通関など、国境を越えるからこその複雑な課題にも直面することになります。特に、販売国ごとの規制や関税対応、現地通貨での決済トラブルなどは、正確な情報と専門知識がなければ大きなリスクとなり得ます。
こうした課題に対処し、安定的に「海外向けEC」を運営していくためには、経験豊富な専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。自力では見落としがちな法的・実務的なポイントも、プロの支援によって円滑にクリアできる可能性が高まります。
まとめとして、越境ECを成功に導くためには、挑戦と同時に適切なリスク管理が不可欠です。もし不安や疑問がある場合は、早い段階で専門家に相談することで、より安心して事業を進めることができるでしょう。