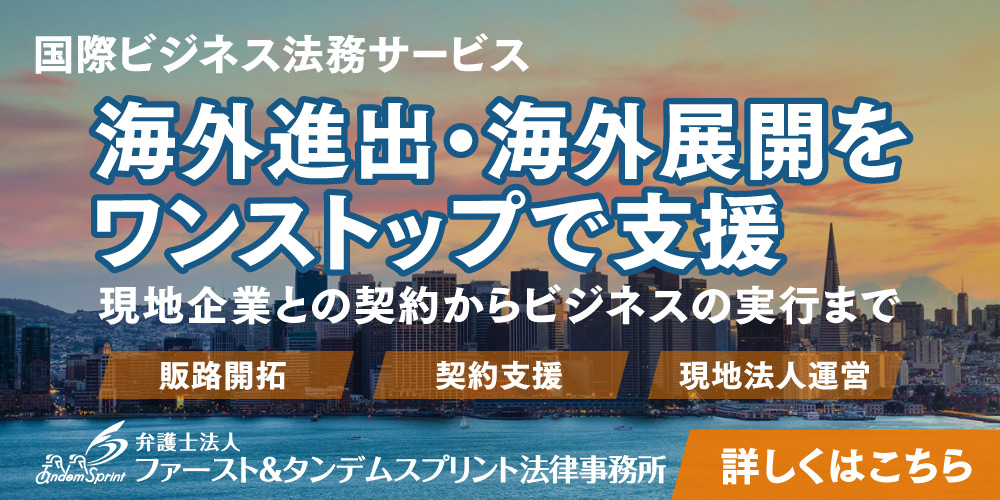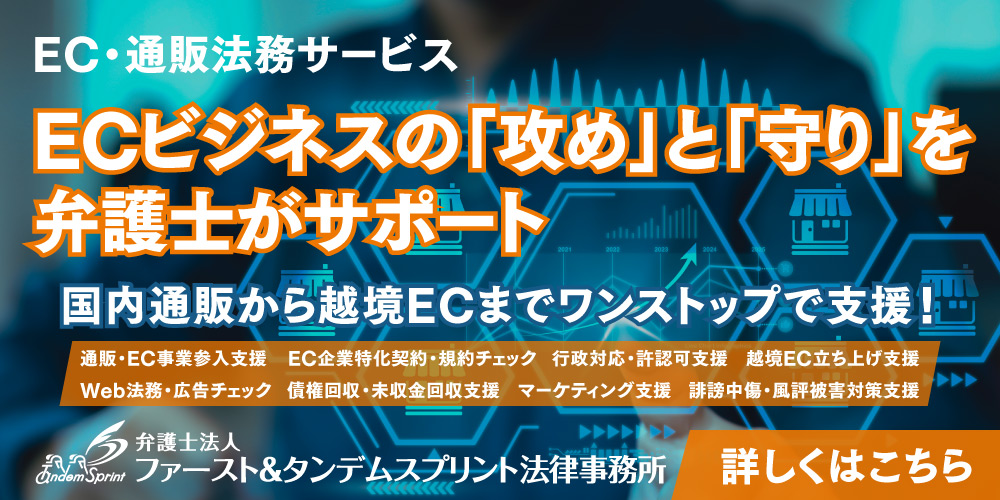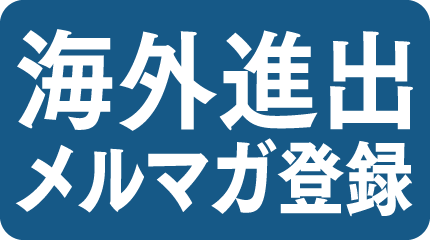目次
越境ECにおける返品率の実態

越境ECの平均返品率
近年、越境EC(クロスボーダーEC)は世界中で急速に拡大しています。日本企業にとっても、新たな販路として注目が高まっていますが、その一方で「返品率の高さ」が大きな課題となっています。返品は単なる顧客対応ではなく、物流コストや在庫管理、利益率に直結する重要な経営指標です。
一般的な国内ECの平均返品率は5〜10%程度とされています。しかし、越境ECの場合は商品ジャンルや販売国によって大きく異なり、平均で15〜25%程度に達するケースが多いと報告されています。特にアパレルや靴などサイズ依存度の高い商品では、返品率が30%を超えることも珍しくありません。
たとえば、中国市場ではEC大手プラットフォームにおける衣料品の返品率が50%以上、女性アパレルにおいては75%近くに達するというデータもあります。返品の仕組みが非常に簡便化されており、複数サイズをまとめて購入して不要なものを返品する「返品前提の購買行動」が一般化しているためです。
世界各国における返品状況
返品率の高さは中国だけの現象ではありません。欧米やその他の国々でも、越境ECの拡大に伴って返品は大きなテーマとなっています。
表:欧州(特に西ヨーロッパ)・北米・その他地域の傾向
(中国以外の地域で見られる具体的な返品傾向を、公開データをもとに以下に示します)
| 地域/国 | 返品率または返品率傾向 | 特記事項・背景 |
|---|---|---|
| 欧州(西欧諸国) | WorldShopping の記事には直接の数字は出ていませんが、他の調査で、オンライン購入品の返品率は 25〜40% の範囲になるとの見方があります。 | 特に衣料・靴ではこの上限に近づく傾向が強い。 |
| ドイツ | 小売業者が部分返品を含めると、一般的に「注文の約4分の1」が返品されるという報告もあります。 | 消費者保護規制と返品慣習が強いため、返品対応体制が整備されている。 |
| 西ヨーロッパ(Global24 データ) | 2024年第2四半期で、複数の国を対象に国際返品率(発送数に対する返品率)を調査したところ、西ヨーロッパ全体で平均約 11.5 % という数値が報じられています。 | 国別ではスペインで37%、イタリアで25%、フランスで21%という高率なケースも報告。 |
| イギリス | Global24 の報告によれば、同じ期間で英国への返品率は比較的低く、「3 %」とする報告もあります。 | ただし商品分野やショップ、返品ポリシーの差によって大きく変動する。 |
| アメリカ(米国) | 日本の貿易関連資料によれば、米国のEC返品率は概ね 17〜19 % 程度との見方があり、日本の国内EC平均(6〜7 %)と比べてかなり高い水準。 | また、Meteor Space の調査では、ECストア全体の返品率の平均を 18.1 % とする報告もあります。 |
| その他国・地域 | DHL のグローバル調査では、各国別に「オンライン購入後返品したことがあるか」の割合を示しており、たとえばカナダで 69 %、ブラジルで 58 %、オーストラリアで 52 % など。 | これらは「購入者の返品経験率」を示しており、「返品率(注文に対する返品率)」とは厳密には異なるが、返品普及度を示す指標となる。 |
欧州の傾向
欧州は返品文化が最も発達した地域のひとつであり、オンライン購入品の25〜40%が返品されるともいわれます。特にドイツでは、注文の約4分の1が返品されるとの報告もあり、返品対応は事業運営の前提条件となっています。これは、EUの消費者保護法が強く、14日以内の返品権が保障されていることが大きな要因です。
2024年の調査によると、西ヨーロッパ全体の国際返品率は平均約11.5%。ただし国別では、スペイン37%、イタリア25%、フランス21%とバラつきがあり、返品に寛容な国ほど率が高い傾向があります。一方で、イギリスは返品率が約3%と比較的低く、返品手続きの複雑さや送料負担の違いが影響していると考えられます。
アメリカの傾向
アメリカのEC市場では返品率が17〜19%前後とされ、国内平均の約2〜3倍。特にブラックフライデーやホリデーシーズンの後は返品が急増します。アパレル・靴の返品率は30%近くに上ることもあり、購入者が「サイズ違い」を想定して複数商品をまとめ買いする「ブロック購入(bracketing)」が一般化しています。返品対応を円滑にするため、無料返品制度を導入するブランドも増えています。
その他の国・地域
DHLのグローバル調査では、「オンライン購入後に返品したことがある」と答えた消費者の割合が、カナダ69%、ブラジル58%、オーストラリア52%と高く、返品が一般的な購買行動として定着していることがうかがえます。一方、日本では返品率が比較的低く、国内EC平均は6〜7%前後とされています。これは、返品文化が欧米に比べて根付いておらず、消費者が「返品=迷惑」と捉える傾向があるためです。
こうしたデータからわかるように、返品率は地域の文化・法制度・物流体制・購買習慣によって大きく異なります。越境EC事業者は、販売対象国ごとの傾向を理解した上で対応を設計する必要があります。
返品率を上げる要因
「商品特性(サイズ・色・質感)」「海外配送トラブル」「購入者の期待差」などが返品率上昇の要因として挙げられていますが、越境ECにおける返品率を押し上げる要因は多岐にわたります。
1.試着できないことによるミスマッチ(サイズ・フィット感)
衣料品・靴分野では、サイズやフィット感のズレが返品の主因とされ、複数サイズを購入して試す「ブロック購入(bracketing)」が行われる例が多く見られます。
学術研究においても、ファッションECにおけるサイズ・フィット関連返品に対して、機械学習モデルを使って返品可能性を予測・制御する試みが報告されています。
2.現地の返品文化・慣習
欧州では返品が「オンライン購入の前提」として消費者に根付いており、返品対応が容易であることが標準となっている国もあります。
たとえば、ドイツやスイス、オーストリアなどでは返品を無料または低コストで受け入れるEC事業者も多く、返品率が高めに出やすいです。
3.配送トラブル(遅延・破損・誤配送)
国際配送では通関や輸送距離、複数の物流事業者を経由するケースが多く、配送遅延・商品破損が発生しやすく、それを理由とする返品が増えやすい側面があります。
4.購入者の不安・期待ギャップ
商品情報(写真・説明)と実際の商品のギャップや、レビューとの不一致が返品動機となるケースがあります。また、現地言語・文化の違いで表現が伝わりにくい場合も影響します。
5.制度・法規制上の返品義務
特定地域(たとえばEU圏など)では、消費者保護法などにより、一定の条件下での返品権やクーリングオフ制度が強く規定されており、事業者側はその法制度のもとで対応せざるを得ないという現実があります。
6.悪質返品・営利的返品
「借りて返す(wardrobing)」と呼ばれる、短期利用目的での購入後返品、または過剰注文・キャンセル目的での購入など、不正返品も一定程度存在します。
返品率の高さは収益性を圧迫し、越境EC事業の持続性に直結するため、企業にとって深刻な経営課題となっています。こうした要因は中国市場だけでなく、欧米・アジア各地に共通して見られるものであり、越境EC事業者は国・地域ごとの特性を把握することが欠かせません。
越境ECにおいて返品ポリシーが重要な理由

越境ECは、国境を越えて商品を販売するという性質上、国内取引と比べて「返品リスク」や「法的リスク」が格段に高くなります。特に返品ポリシーや利用規約の整備は、越境EC事業者向けに最も重要な法的対策の一つといえます。配送に時間がかかるうえ、商品情報や説明の「言語・文化の壁」が存在し、購入者と販売者の間で誤解が生じやすいためです。このような環境では、明確で信頼性の高い返品ポリシー(Return Policy)が、単なるルールではなく「顧客との約束」としての役割を果たします。
返品ポリシーとは
返品ポリシーとは、購入者が商品を返品または交換する際の条件・手順を定めた規定です。主に以下のような内容を明文化します。
- 返品可能な期間(例:商品到着後14日以内)
- 返品・交換が認められる条件(初期不良、誤配送、サイズ違いなど)
- 返送料の負担者(販売者 or 購入者)
- 返金の方法とスケジュール
これらを明確に提示することで、購入者に「安心して購入できる」という心理的安全性を提供します。また、返品ポリシーと併せて利用規約を整備しておくことで、取引条件や責任範囲をより明確にでき、海外販売向けの信頼構築にもつながります。特に越境ECでは、購入者が日本ブランドや外国事業者に対して「返品できるのか」「返金されるのか」という不安を持ちやすく、返品ポリシーは信頼形成の第一歩となります。
返品ポリシーがもたらす効果
1.信頼性の向上
透明で公平な返品ルールを提示することで、購入者の不安を軽減できます。
特に欧米では「返品できないECサイトは信用されない」とまで言われており、返品のしやすさが購入率に直結します。たとえば米国Amazonでは「30日間返品保証」が標準であり、これが消費者の購買行動を後押ししています。
2.トラブル防止
返品条件を明確に定めることで、購入後のクレームやトラブルを未然に防げます。
たとえば「タグを外した商品の返品は不可」「セール品は返品対象外」など、事前に明記しておくことで、販売者・購入者の双方にとってフェアな関係を築けます。
3.ブランドイメージの向上
誠実な返品対応は、ブランド価値の向上に直結します。
反対に、返品対応が遅れたり不透明だったりすると、SNS上での批判(いわゆる「炎上」)リスクが高まります。
海外では「返品対応=カスタマーケア品質の指標」とみなされる傾向があり、特に越境ECブランドにおいては、返品対応そのものが“信頼ブランド”の要素の一つとなっています。
4.法的リスクの回避
国によっては、返品やキャンセルに関する消費者保護法が厳しく定められています。
たとえばEUの「消費者権利指令(Consumer Rights Directive)」では、購入後14日以内の返品権が義務化されています。アメリカでも州ごとに返品ルールが定められ、表示義務を怠ると罰則の対象になる場合があります。
対象国の法制度に準拠した返品ポリシー設計は、訴訟リスクを防ぐための最重要ポイントです。
越境ECにおける返品ポリシー作成の際の5つのポイント
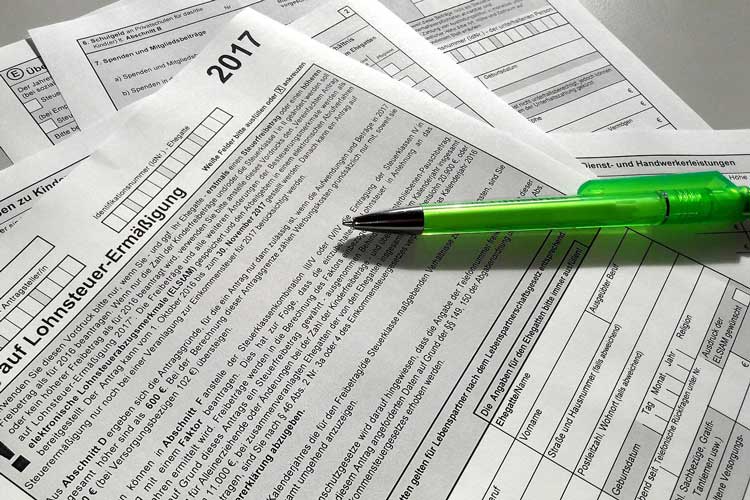
1.返品・交換の「条件」と「期間」を明確にする
返品対象となる商品カテゴリー(例:アパレル、雑貨、電化製品)や返品理由の範囲を明記します。
また、「商品到着後◯日以内」「未使用・未開封に限る」など、具体的な期間と条件を記載することが信頼を得るカギです。
曖昧な表現は誤解を招き、トラブルの温床になります。
2.「送料負担」のルールを具体的に定める
越境ECでは、送料の負担が大きなトラブル原因になります。
「初期不良は販売者負担」「サイズ違いは購入者負担」など、ケースごとに明確なルールを設けることが重要です。
特にEUでは、消費者保護法により販売者側が返送料を負担しなければならない場合もあるため、対象国の法規制を必ず確認しましょう。
3.「返金方法」と「処理期間」を明記し、顧客の不安を払拭する
クレジットカード、PayPal、ストアクレジットなど、どの手段で返金するかを明示し、処理期間(例:7営業日以内)を明確にしておくことで、購入者の不安を軽減できます。
返金処理の透明性はリピーター率の向上に直結します。
4.準拠法と紛争解決手段を明記する
国境を越えた取引では、どの国の法律が適用されるかを明示しておく必要があります。
契約書や返品ポリシーに「準拠法:日本法」「専属管轄裁判所:東京地方裁判所」などを明記することで、不測の紛争リスクを大幅に軽減できます。
また、裁判以外の解決策として「国際仲裁(Arbitration)」や「越境消費者センター」などを利用する選択肢も有効です。
5.機械翻訳に頼らない、分かりやすい言葉と導線で伝える
越境ECでは、英語や中国語など多言語対応が欠かせません。
ただし、機械翻訳による誤訳は誤解やクレームを引き起こす原因になります。
現地の文化や言語に精通した翻訳者による自然な表現を用いることで、ブランドへの信頼感を高められます。
さらに、返品フォームやFAQページへの導線をわかりやすく設計することで、問い合わせ件数の削減にもつながります。
返品率を下げるためのその他の方法

返品ポリシーを整備するだけでなく、返品そのものを減らすための工夫も欠かせません。
- 商品情報の充実:サイズ表、素材感、モデルの着用例などを詳しく掲載し、期待とのズレを防止
- 顧客レビュー活用:写真付きレビューやQ&Aを充実させ、実際の使用感を共有。
- 物流の最適化:追跡可能な配送、丁寧な梱包、現地倉庫の活用で破損や遅延を防ぐ。
- AIによるレコメンド:購入履歴や体型データを基にしたサイズ推定機能で誤購入を防ぐ。
- 現地カスタマーサポート:購入後の相談や交換対応を現地言語で行うことで、返品を未然に防ぐ。
これらの施策を組み合わせることで、単に「返品を減らす」だけでなく、顧客満足度とブランド信頼性の両立を実現できます。さらに、返品ポリシーや利用規約を定期的に見直し、販売国向けに最適化することで、越境ECの運営リスクを大幅に軽減できます。
越境EC事業に関するお悩みは専門家にご相談ください

越境ECは、世界中の顧客とつながることができる大きなビジネスチャンスである一方、言語・法律・物流・決済など、多面的な課題を抱える複雑な領域でもあります。特に返品対応は、売上・ブランド・法的リスクのすべてに直結する重要なテーマであり、「国内ECの延長線上」として対応するのは非常に危険です。
1.国・地域ごとに異なる消費者保護法の壁
越境ECで最も見落とされがちなポイントが、「各国の返品規制の違い」です。
例えば欧州連合(EU)では、消費者は商品到着から14日以内であれば理由を問わず返品できる権利(クーリングオフ制度)が認められています。
一方で、アメリカでは州ごとに返品ルールが異なり、中国や東南アジアでは返品手続きの簡便さが競争力の一部になっています。
これらの制度を理解せずに販売を行うと、消費者トラブルや行政指導、さらには訴訟リスクに発展するケースもあります。
国際取引では「準拠法」「管轄裁判所」「返金ルール」などの法的整備を怠らないことが、事業リスクを最小限に抑える鍵となります。
2.物流・コスト構造の最適化が収益性を左右
返品コストは、越境ECの利益を圧迫する大きな要因です。
海外からの返品1件あたりのコストは国内返品の3〜5倍に達することも珍しくありません。
そのため、海外倉庫の活用、現地での検品・再販ルートの確保、返品集約拠点の構築といった物流戦略が不可欠です。
さらに、返品を減らすためのデータ活用も進んでいます。
AIによるサイズ推定や購入履歴分析を通じて、購入前のミスマッチを減らすことで、結果的に物流コストを大幅に削減できます。
こうした仕組みを導入するには、ECシステム・物流・データ分析を横断的に理解した専門家の支援が不可欠です。
3.多言語・多通貨対応に潜むリスク
越境ECでは、単に翻訳を行うだけでなく、各国の文化的背景に配慮した表現が求められます。
返品ポリシーひとつ取っても、「やわらかい表現を好む地域」と「明確な指示を求める地域」では、適切なトーンが異なります。
また、返金処理の際には為替変動や決済プラットフォームの手数料が発生する場合もあり、金融・税務の専門知識も必要です。
そのため、言語翻訳・ローカライズ専門会社、国際税務の専門家、そして現地の法律顧問など、多分野のプロフェッショナルと連携した体制構築が理想です。
4.顧客体験(CX)向上のための返品戦略
「返品対応=コスト」と考えるのはもはや過去の発想です。
AmazonやZARA、SHEINなど世界的大手ECでは、返品のしやすさをブランド戦略の一部として位置づけています。
スムーズな返品体験は、「またこのブランドで買いたい」という心理を生み出し、リピート率向上につながります。
たとえば:
- 返品プロセスをオンラインで完結できるようにする
- 返金ステータスのリアルタイム通知で安心感を提供
- 返品理由データの分析を通じて、商品改善や在庫管理に活かす
こうした「返品データの戦略的活用」は、単なる顧客対応を超えた“マーケティング資産”となります。
5.専門家とともに「グローバル対応型EC基盤」を整える
返品対応を含む越境ECの課題を解決するためには、
- 法務(準拠法・規約策定)
- ロジスティクス(倉庫・返品ルート最適化)
- カスタマーサポート(多言語対応・チャットサポート)
- テクノロジー(AI・CRM・自動翻訳)
といった要素を包括的に整備する必要があります。
特に中小規模のEC事業者にとっては、これらを自社だけで構築するのは困難です。
そのため、越境EC支援サービスを活用し、専門家からの情報やアドバイスのもとで運用を設計するのが最も現実的なアプローチです。
国や文化を超えたビジネスでは、透明性・誠実さ・迅速な対応こそが最大の競争力です。
返品を恐れず、正しく設計されたポリシーと運用体制を整えることで、越境EC事業はより持続可能で信頼されるグローバルビジネスへと進化していくでしょう。